
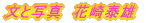
2007年3月―
稀代の文人・渡辺一夫が破格の名調子で翻訳したフランソワ・ラブレーの奇想天外な物語『ガルガンチュワとパンタグリュエル』全5巻は岩波文庫で読むことができる。文庫第一巻『第一之書 ガルガンチュワ物語』は、ラブレーの読者に対する次のような呼びかけで始まる。「この書を繙き給う友なる読者よ」。ラブレーはここで、この書物の目的は読者に笑っていただくことありで、それ以外にはたいしてうるところはなかろうといっている。その理由は「涙よりも笑いごとを描くにしかざらむ、笑うはこれ人間の本性なればなりけり」。そして、ラブレーの11行の読者へのあいさつは、次のようにしめくくられている。
――楽しく生き給え。
第1章 新聞記者村編集局通りに住みつく
*
1 ぬるいコーヒーに始まる
2007年2月、雨季のジャカルタは大洪水に見舞われた。2002年以来の規模だったそうである。2002年の洪水のさいは、水没した家の屋根から釣り糸をたれていたら鰐がこっちへ泳いできたので仰天した、というちょっと信じられない噂話を聞いた。
2007年はジャカルタの4分の3の地域が洪水被害に見舞われ、30万人が家を捨てて避難、80人を超す死者が出た。私がそのむかし住んでいた地区は東ジャカルタのちょっとした高台にあった。かつての隣人から電子メールが届いた。地区は水没しなかったが周囲すべてが冠水した。したがって地区全体が孤島状態になって周囲から隔絶された、という。
ちょうどそのころ、ジャカルタの大量高速交通システム(MRT)計画の新聞記事を日本で読んだ。日本のODAをベースに事業を進めるという。MRTには地下鉄部分もあるそうだ。地下鉄トンネルが巨大な雨水溝と化すのをどうやって防ぐのだろうか?
日本の国際協力銀行などが開いたそのMRT事業の説明記者会見で、出席したジャカルタの記者たちに現金入り封筒が配られたという懐かしい記事を共同電で読ませてもらった。それによると、「記者会見はジャカルタのホテルで開かれた。準備を請け負った日系広告会社が記者用資料の中に20万ルピア(約2,700円)入りの封筒を入れて配った。地元記者は50人以上が出席、大半が受け取ったとみられる」。

夕立を待つジャカルタの街
封筒はインドネシア語でアンプロップ。俗に賄賂的こころ付けを意味する。辞書にも堂々のっている。おお、まだやっていたのか。懐かしさもあって、暗雲ときに垂れ込める、雨季の終りの3月、ジャカルタに出かけた。
さて、開業30余年、施設は古くなったが、ゆったりとしたジャカルタの名門ホテル・ボロブドゥールに泊まった。朝食。極めつきのぬるいコーヒーが出てきた。熱いのと取り替えて頂戴、と頼んだ。「ハイ」といい返事。だが、もって来た次のコーヒーもぬるかった。そういうわけで、ぬるい朝のコーヒーを2週間ほど飲み続けた。やがて、そのぬるさ加減によって乾燥凍結されていた記憶が次々とときほぐされてゆく。

ぬるいコーヒー
2 パサール・イカン
その当時、ジャカルタはまだバタヴィアとよばれていた。オランダ領東インドの中心都市であった。そこを金子光晴と森三千代が一九三〇年前後に訪れている。
金子光晴と森三千代といっても、いまの若い世代にはピンとこないだろう。金子が詩人で、森が小説家だ。金子光晴は森三千代に恋をし、子どもを生ませ、子どもを生んだ三千代は後に美術評論家となる若き日の土方定一に心を移した。
光晴は子どもを抱いて土方定一のところにいた三千代に、男をとるか、それとも子どもをとるか、とせまったそうである。戦前の芸術家仲間の自由気ままな恋愛ごっこ。光晴は三千代を土方定一から引きはなすため、なけなしの金をはたいて三千代を海外旅行に連れ出した。生まれた子どもを三千代の両親に預けっぱなしにしたまま、5年間にわたって中国、東南アジア、ヨーロッパを放浪した。旅費は旅先で何とか工面するというゆきあたりばったりの貧乏旅行である。
時代は日本が軍国主義の道を歩み始めるころであった。アジアへの帝国主義的野心が東北アジアから東南アジアへとふくれあがる。やがては太平洋戦争にはじけてゆく。そうした暗い予感がただよう時代を背景に、漂泊の中で物書き同士の三角関係解消と和解を求めようとした傷心の旅だった。

パサール・イカン
サマセット・モームの南海ものの短編を思わせるような詩人と小説家の二人づれがたそがれのバタヴィアの路上にながい影をおとした。金子と森はバタヴィアの街をあてもなく歩く。「ここだけは、生涯忘れることができない」。森が金子にそう語ったのが、パサール・イカン(魚市場)があるバタヴィア旧港のたたずまいであった。
オランダ植民地時代末期のバタヴィア旧港にたむろする人々と風景を、金子は『マレー蘭印紀行』の美しい文章に残している。乞食の並ぶほこりっぽい道、船待ちの休息所、サロン売り、洗面器に入れたカレー料理、回教寺院、たくましいマドゥラの漁夫とその妻たち。オランダ植民地政策のもとで生気を失ったジャワの人々も「旧港だけが彼らの天地のようにいきいきとうごいている」と金子は書いている。
金子光晴と森三千代が見たバタヴィア旧港のあるスンダ・クラパとパサール・イカンは今ではジャカルタの場末となって眠りこけている。スンダ・クラパに残っているものは、インドネシア国内航路の木造貨物船であるブギス・プラフの船泊と、ジャカルタ沖のプロウ・スリブの島々への渡船乗り場、薄汚れた雑貨店の並ぶパサール・イカンである。

ブギス・プラフ
放浪の後、金子光晴が書いた『マレー蘭印紀行』は、東南アジアを放浪する文学青年たちのバイブルとなった。『マレー蘭印紀行』に書かれた見聞は、実際の風景ではなく、金子光晴の頭の中でデフォルメされた彼の苦悩と哀愁の幻影である。文学青年たちはその幻影を追体験したがった。若きころの立松和平もその一人で、『マレー蘭印紀行』を片手にマレーシアのバトパハに出かけ、安宿の汗のにおうベッドで暑苦しく、眠れぬ夜をすごし、昼間はしょざいなく『マレー蘭印紀行』を繰り返し読んだという。いったい何人の日本の若者がバトパハを訪れたことだろう。
金子光晴と森三千代はその後よりを戻し、今では八王子の霊園で同じ墓の中で永い眠りについている。金子光晴と森三千代の子どもである森乾が書いた『父・金子光晴―夜の果てへの旅』(書肆山田、2002年)によると、森三千代は土方定一と切れた後も次々と新しい恋愛・情事を繰り返して光晴を嫉妬させたという。一方、金子光晴も60歳のころ、どこかで淋病をもらってきて、それをリューマチで病臥していていた三千代に感染させたそうである。金子光晴は腋臭のうえ、垢と歯ブラシを使わないための虫歯の口臭で、傍によると嘔吐をもよおすことが多かった、と森乾は書いている。
『マレー蘭印紀行』は金子光晴の戯画的人生が紡ぎだした滑稽の果ての美文だったのだ。
3 オリヴィア <上>
バタヴィアには私の好きないまひとつの三角関係の物語がある。こちらの方は、前回お話ししたリアルな人間模様はあるが、垢じみて貧困臭のただよう金子・森の物語とは次元をことにする。ヒューマン・ドキュメントとしては内容空疎だが、外見は冒険と、形式としての華麗・典雅にあふれている。それらの飾りを引き剥がしていったのち、最後に核としての一つの謎に行きあたる。その謎によって人間の情愛をめぐる思いのあれこれにひきこまれるのである。
トマス・スタムフォード・ラッフルズ(1781-1826)という人物をご存知だろうか。シンガポールの最高級ホテル、ラッフルズはこの人の名に由来する。ラッフルズはシンガポール建設に手を染めたイギリスの植民地行政官である。マラッカ海峡の出入口に位置するシンガポール島の地理的重要性に着目して、植民地主義者の手練手管を使って、ジョホール王国から島の割譲をうけた。これが現代の通商都市国家シンガポールの始まりである。

シンガポールのラッフルズ像
シンガポールには現在でもラッフルズの像が街中に建っている。旧宗主国の植民地官僚の像を現在なお国民が見上げている。もともとはマレー人の土地だったところをイギリス人が植民地にして発展させた。植民地時代の終焉とともに人口の過半数を占めるにいたった中国系移民の末裔がシンガポールを引き継いだ。そういうことで、植民者としてのラッフルズに対するこだわりは希薄なのかもしれない。
さて、そのラッフルズだが、イギリス東インド会社の幹部職員として1805年からマレー半島のペナンで勤務した。ナポレオン戦争でオランダがフランスに占領されたのを機に、オランダ領東インドへの侵攻を上司に進言した。作戦は1811年に始まり、さしたる抵抗もなくイギリスはジャワを占領した。このときから1816年、ジャワがオランダに返還されるまでラッフルズはジャワ副総督をつとめた。
ラッフルズはジャワ副総督時代にボロブドゥール遺跡の復元、ラフレシアなど動植物の新種の発見のような学術事業を推進した。オランダ時代の奴隷制や拷問の廃止、税制改革などを進めた。信夫清三郎はラッフルズのこの開明的な部分に賛同して、太平洋戦争中の1943年『ラッフルズ伝』を出版した。だが、現在の普通のインドネシア人にとっては、ラッフルズは遠い過去の人である。ラッフルズの時代は長いオランダ支配の中の短い一幕劇にすぎなかったからだ。
ラッフルズは年上の妻、オリヴィア・マリアン・ラッフルズとともにジャワに住んだ。ラッフルズが10歳年上のオリヴィアと結婚したのは1805年、23歳のときである。オリヴィアは1771年生まれ。1793年に最初の結婚し1800年に夫と死別している。オリヴィアはイギリス人を父親に、チェルケス人を母親に、インドのマドラスで生まれたという説が有力だが、出生に関してなお不明な点が多い。
C. E. Wurtzburg, Raffles of the Eastern Isles, London, Hodder and Stoughton, 1954. によると、オリヴィアの肖像は残っていないが、オリヴィアに会ったラッフルズの上司東インド会社総督ミントー卿によると「ラッフルズ夫人は立派なレディーだ。黒い瞳の人で、立ち居振る舞いは知性的で、洗練され、生き生きとしている。酒と恋に生きた(アイルランドの詩人トマス)ムーアが大量の愛の詩を捧げた女性たちの一人だった」そうである。オリヴィアはなかなかに雰囲気のある人だったようだ。
ラッフルズは14歳のとき東インド会社に臨時職員として雇われた。上司であるウィリアム・ラムゼーに目をかけてもらい、ラムゼーの屋敷に集まる知的な人々の会合に出席を許された。そこで交わされる時代と世界の新しい話題によって、ラッフルズは育っていった。こうしたことから、悪意ある噂話がラッフルズにつきまとう。オリヴィアはそのラムゼーの愛人だった。オリヴィアと結婚することを条件に、ラムゼーがラッフルズのために東インド会社での昇進の扉を開いてやったのだ。そういった内容の噂だった。この噂は最終的に1816年、とある書物の中で活字化された。
ラッフルズは従兄弟への手紙で、オリヴィアはラムゼーと面識がなく、昇進とオリヴィアとの結婚は関係がない、と否定している。
ともあれ、このようにして19世紀初頭の東南アジアに関するイギリスの大戦略家トマス・スタムフォード・ラッフルズはマレー半島のペナンにある東インド会社支社の事務次長としてアジアに渡った。

タマン・プラサスティ外人墓地の像
そのペナンで暮らし始めたトマスとオリヴィアは、ジョン・キャスパー・レイデンという医師と深い交流を持つことになる。レイデンは1775年生まれ、年齢的にはトマスとオリヴィアの中間にあった。
4 オリヴィア <下>
ジョン・キャスパー・レイデンは、オリヴィアとトマス――ラッフルズ夫妻と偶然の引き合わせてめぐり合い、友情と恋情が切り離しがたく交じり合った交友を続けることになった。
レイデンは1775年生まれ。エディンバラ大学などで神学、文学、医学を学んで医者になった。レイデンは『湖上の麗人』や『アイヴァンホー』などを書いたウォルーター・スコットの友人で、スコットの出世作『スコットランド・ボーダー地方の吟遊詩』(Minstrelsy of the Scottish Border)の著作に協力した。この本はスコットランドの民話や民謡を収集したものである。スコットはレイデンを「詩人である」と評したといわれている。スコットはレイデンの詩心を理解していたようだ。
レイデンは医者としてイギリス東インド会社に雇われ、1803年にマドラスに向かった。この航海中にレイデンは体調を崩してしまう。マドラス到着後も体調は回復に向かわず、むしろ悪化した。マドラスの病院で治療を受けたが病状は回復しなかった。東インド会社は転地療養のため、レイデンをペナンに送った。1805年10月のことであった。
ちょうど1ヵ月前の1805年9月に新婚のラッフルズ夫妻がペナンに赴任していた。粗末な官舎で一人暮らしをする病気のレイデンを気の毒がって、ラッフルズ夫妻が自宅に引き取った。オリヴィアが手厚い看護をした。レイデンはこうして3ヵ月にわたってラッフルズの家で病身を養った。回復したレイデンはやがて1806年1月、インドへ帰任する。
この3ヵ月間に、ラッフルズはレイデンの学問への真摯な態度に深い感銘を受け、レイデンはラッフルズの知性とアカデミックな探究心に深い敬意を抱いた。レイデンはペナン滞在中のマレー研究の成果をもとに、Sejarah Melayu(『マラヤ史』)をマレー語から英語に翻訳したほか、Dissertation
on the Indo-Persian, Indo-Chinese, and Dekkan Languagesを著した。これの本はレイデンの死後に出版された。すでに著名人になっていたラッフルズが序を書いて添えた。ラッフルズはレイデンに兄事し、レイデンに知的に育てられ、のちに行動においてレイデンをはるかに凌駕する存在になった。漢文調でいえば、刎頚のまじわりだった。
「レイデンはオリヴィアを恋するようになった」と、前回紹介したWurtzburgはラッフルズの伝記で書いている。当時のイギリス人にとってペナンは地の果てともいってよい異郷である。そこで病の身をいたわり、手を尽くして看護してくれる麗人がいれば、その人に恋心を抱かない若者はいないだろう。
レイデンはオリヴィア宛の手紙に、数行の詩を書いている。レイデンのトマス・ラッフルズに対する敬愛とともに、オリヴィアへの恋心が行間からにじみ出てくるようである。
Still may’st thou live in bliss secure
Beneath that friend’s protecting care
And may his cherished life endure
Long, long, thy holy live to share.
一方、オリヴィアはレイデン宛の手紙に、
My Dear Dr. Leyden,
I feel an affection for you such as I feel for my only and beloved
Brother.
And when I heard you were dangerously ill I felt such a sudden pang
as
assured me of the sincerity of my regard….
と書いている。レイデンもオリヴィア宛の手紙をMy Dear Sister Oliviaと書き始めるのが常だった。
トマス・ラッフルズもまた、オリヴィアがレイデンのことを魅力的な友人として受け入れたこと、レイデンが情愛をこめてオリヴィアに接してくれること、レイデンとともにマレー語の研究に打ち込めること、それらを大いに喜んだ、というのがWurtzburgの見方である。
ペナン駐在のラッフルズ夫妻、マドラスからカルカッタ勤務転じたレイデンの3人は、1806年から1811年の間、手紙で友情を確かめ合ってきた。1910年にラッフルズがペナンからカルカッタに来て、ジャワ侵攻をミントー卿に進言したさい、すでにミントー卿の信頼厚い部下になっていたレイデンが強力な援護をしてくれた。
イギリスは1811年ジャワに侵攻した。イギリスのジャワ制圧直後の1811年8月28日、遠征に同行していたレイデンが急死した。死因は肺炎ともマラリアともいわれている。ラッフルズはレイデンの亡骸をバタヴィアのヨーロッパ人墓地(現在のタマン・プラサスティ墓地公園)に埋葬した。
ジャワ副総督となったラッフルズ夫妻は、主としてボゴールに住んだ。ボゴールはジャカルタより標高が高く、少し涼しい。オリヴィアは副総督夫人としてバタヴィア在住のヨーロッパ系住民のだらしない生活習慣を改め、洗練されたヨーロッパ風に戻す運動を進めたという。オリヴィアもまた開明的な植民地行政官の妻だったわけだ。

ボゴールのオリヴィア・ラッフルズ記念テラス
オリヴィア・ラッフルズはレイデンの死から3年後の1814年11月月26日にボゴールの屋敷で急死した。トマス・ラッフルズはオリヴィアをバタヴィアの外人墓地のレイデンの墓の隣に埋葬した。さらに、ラッフルズ夫妻が暮らしたボゴールの屋敷にオリヴィアとの幸せな日々を記念するテラスを造らせた。オリヴィアを記念するテラスは現在もボゴール植物園内に残っている。濃い緑の中に白い円柱が印象的な優雅なテラスは生前のオリヴィアの姿を想像させる。ラッフルズはそのテラスに、オリヴィアが1808年にレイデンに贈った詩の数行を刻ませた。
OH THOU WHOM NE’ER MY CONSTANT HEART
ONE MOMENT HATH FORGOT
THO’ FATE SEVERE HATH BID US PART
YET STILL FORGET ME NOT
トマス・ラッフルズはなぜオリヴィアをレイデンの墓の隣につくって比翼塚としたのだろうか? なぜ、トマス・ラッフルズはオリヴィアがレイデンに贈った愛の詩を、そのままのかたちで、トマスからオリヴィアへの永遠の愛の歌として刻みこんだのだろうか。
トマス、オリヴィア、ジョンの3人は生涯にわたって破綻することなく、それぞれを同じように深く愛しあっていた、としか言いようがない。そのような愛が至高の愛であるのか、独占を願う世俗の愛を思えば、それは愛としてはやはり偽物であるのか、私には判定のしようがない。
トマス・ラッフルズの2番目の妻ソフィアは、克明なラッフルズの伝記、Memoir of the
Life and Services of Sir Thomas Stamford Rafflesを書き残した。だが、後妻であるソフィアは最初の妻オリヴィアが関わる部分については完全に記録から削除した。したがってMemoirではオリヴィアの名はただ1ヵ所だけ、それも脚注に現れるだけだ。これもまた、ひとつの愛の形ではあろう。しかし、このことによって、われわれはトマス・スタムフォード・ラッフルズ、オリヴィア・マリアン・ラッフルズ、ジョン・キャスパー・レイデン、この3人の愛の物語の深い謎を解きほぐす糸口を失うことになったのである。

タマン・プラサスティ墓地のジョン・キャスパー・レイデン(手前)と
オリヴィア・ラッフルズ(奥)の墓
5 ハリマオ
たいていの追憶がそうであるように、この『ジャワ追憶』も話題は行きあたりばったりである。とはいうものの、金子光晴・森三千代からラッフルズへと、話のまくらにしては長すぎた。そのうえ、ちょっと浮世離れした年代物にすぎたきらいもあった。ここらでいったん話を現代まで引き戻そう。
2007年4月1日、東京・赤坂のインドネシア・レストランで、ドミニクス・バタオネ、メリアナ・バタオネ夫妻の送別会があった。D.バタオネ氏は元インドネシア大使館員で、東京におけるインドネシア語教育ではちょっと名の知れた人である。75歳になったのを機に、スラウェシ島のマナド市郊外のコバルトブルーの海の見えるあたりに住みつき、涼やかな海風にあたりながら隠居生活を楽しむとのことだった。彼はフローレス諸島のレンバタ島の出身で、海には限りない愛着がある。

送別会でのバタオネ先生夫妻(東京・赤坂で、2007.4.1)
マナドはいいところだ。私も一度だけ行ったことがある。ジャカルタのジャーナリストたちと一緒の旅だった。泊まったホテルが民放テレビ局の当時の人気キャスターの実家の経営で、そのホテルの広い庭にドリアンの林があった。そこからドリアンをとってきて、庭のテーブルにドリアンの山をきづき、ホテルの従業員がうまそうな実を選んで開いてくれた。皆で死ぬほど食った。ああ、また話がそれた。
私もバタオネ先生からインドネシア語の手ほどきを受けた。厳しい先生という定評のあった方で、先生が自ら書き下ろした『バタオネのインドネシア語講座 初級』(めこん)には「あの先生は厳しいので、生徒は虎(ハリマオ)というあだ名をつけた」というふうな例文があった。「勉強が足りませんねえ」とよくしかられた。
日本でバタオネ先生からインドネシア語を習ったあと、バンドンへ行って、バタオネ先生のお連れあいのメリアナさんの妹さんのエミリアさんの家に転がり込んで居候をし、バタオネ先生の友人のパジャジャラン大学の先生2人からインドネシア語の個人教授を受けた。さらに、ジョクジャカルタのガジャマダ大学の語学クラスでも特訓を受けたが、つまるところ、「あなたはいつまでたっても書くようにしか話せませんね」というていたらくだった。
ジャカルタに住んでいるときも、お手伝いさんに「ボス、晩ご飯は何にしましょうか?」とたずねられ、何度も「え?」「え?」と問い直すありさま。お手伝いさんは、朝から難しい顔をして何種類ものインドネシア語の新聞を読みふけっているのに、この人なんでこんな簡単なインドネシア語がわからないんだろう」と不思議がっていた。
50歳で新聞社でのキャリアに見切りをつけ(新聞社のほうも記者としての私に見切りをつけていた)、繰上げ定年を申請した。割り増しの退職金をもらって、住宅ローンなどのしがらみを清算し、インドネシアの政治研究のために、オーストラリア・メルボルンのモナシュ大学の博士課程に入学した。インドネシア研究はインドネシアの大学でするより、オーストラリアの大学でやったほうがよろしい、というのが、バタオネ先生の助言であった。1993年のことだった。
めでたくモナシュ大学でPh.D.をとって1996年に帰国、1年ほどブラブラしたあと、某国立大学の教員になった。再就職をしたが、給料は学士号のときの半分以下になってしまった。ともあれ、以来、留学生担当教員のかたわら、インドネシアを中心にした東南アジア地域の政治学を学部と大学院で教えておよそ10年。2007年3月31日めでたく65歳で定年退職した。大学教授と何とかは3日やったらやめられない。4月1日からは某私立大学に移って、今度は本職だったマス・メディア論、新聞論の教師になった。

ボゴールの植物園 Taman Raya Bogor の木。
植物園一帯はオランダ領東インド時代の総督の
お屋敷の庭だった。ラッフルズが住んだころ
から植物園として整備され始めた。
バタオネ先生にインドネシア語を教えてもらっていたころ、先生は50代の終り、私は40代の終りだった。先生は痩身で、その動きには、スマトラの森から出てきた虎のような強靭なバネが感じられた。あれから15年余り、バタオネ先生はすっかり丸顔になっていた。私の方もコレステロールと尿酸値を下げる薬が手放せなくなった。送別会では、最後に先生がインドネシア語で挨拶した。バタオネ先生の挨拶は「トゥリマカシ」(ありがとう)をのぞいて、ほとんど聞きとれなかった。いやはや面目ないことである。
くわえて、大学を移ることで、「ここらでインドネシア政治研究はひとまずおいて」という気分になってくる。そういうわけで、これから先のインドネシアを展望するような話題よりも、来し方をふり返る『ジャワ追憶』で時間をつぶすことになった。
6.オモン・コソン
オモン・コソン(omong kosong)というインドネシア語は、英語のnonsense、大阪語の「アホ談義」、名古屋語の「タワケ話」にあたる。なかでも「タワケ話」が最適訳だろう。私がジャカルタに住みついてフィールドワークをしていたころ、ハルモコ(Harmoko、ジャワ人は名前だけで、通常、姓を名乗らない人が多い)という男がいた。スハルト元大統領の腰巾着で、ジャカルタの大衆紙『ポス・コタ』のオーナーで、情報大臣で、後に国会議長になった。どこかの国のイスラム教徒に「猿の脳みそを持つ男」と罵られたアメリカ人がいるが、ハルモコの脳みそはそれよりももっと軽い、とジャカルタの人たちはいまでも思っている。そこでできあがったインドネシア流アナグラムがHARUMOKO=HARI-HARI OMONG KOSONG。HARI-HARIとは毎日まいにち、来る日もくる日も、の意味。ハルモコ氏については、面白いエピソードがたくさんあるので、そのうちおいおいと思い出すことにして……。
さて、バタオネ先生の送別会の翌日の4月2日、某私立大学教授就任の辞令をもらいに、自宅から100キロも離れた群馬県高崎市の埼玉県境付近にある大学まで出かけた。仮にJ大学としておく。午前11時ごろから、たいていの辞令交付式がそうであるように偉い人がじきじきに辞令を手渡し、お互いに深々とお辞儀しあう大時代的な式があった。
辞令といえば、1964年に入社した新聞社の辞令交付はそっけなかった。部長が新人記者(ひとりでは動けないキシャなので昔はトロッコとよばれていた)の辞令20人分ほどをポイと机の上に投げ出して、「それぞれで自分のものをさがしてくれ」ときたもんだ。大学の職員が単位の計算を間違えて、あんたは卒業できないと通告してきたことに腹をたて、大学の卒業式には出なかった。だから卒業証書はもらっていない。オーストラリアの大学の博士学位の証書は郵便で日本に送ってもらった。指導してくれた先生から「来ると思ってパーティーの準備をしていたのに」と失望のお手紙をもらった。最近まで勤めていた某国立大学の辞令はメールボックスの中に差し込まれていた。定年退職にあたって学長との会食・記念撮影の招待があったが、彼とは犬猿の仲だったので、出なかった。この話の詳細ものちほど。
J大学の大仰な辞令交付式典が終わるともう昼で、事務の人に昼飯の食える場所を聞いたら、近くにうどん屋が1軒あるきり。いったら満員だった。うんざりして何も食わずに帰ってきたら、親切な女子職員が「教授会は長いですよ。はらぺこだともちませんよ」(教授会の長いのは身にしみて知っている)と言って、コンビニのありかを教えてくれた。徒歩で往復20分。おむすびをかじりながらとぼとぼと帰ってきたら、教授会の新年度初顔合わせが始まろうとしていた。そのあと委員会、教授会再開。行事が終わったらもう午後5時だった。研究室に帰って、辞令交付式で渡された封筒を開くと中からとんでもない内容の物が出てきた。労働条件通知書である。
そこには「月給35万円余」と書かれていた。見ると通知書の日付は4月1日。だが、渡されたのは2日であるからまんざら嘘ではないだろう。私をスカウトに来たJ大学理事会の使いの男は「教授で迎えます。定年は65歳だが70歳まで延長できるので問題ありません」とだけ言ったが、こんな低賃金については一切口にしなかった。文部科学省に提出するメディア関連の学科新設届け記載用に、新聞社出身で、博士号を持ち、国立大学で教壇に立っていた私のキャリアが欲しかったのだろう。

ジャカルタ国立博物館で
「オモン・コソン!。安売りはしないぞ。これは就任お断りの一手だな。しかし、私のことをこのJ大学に紹介してくれた同じJ大学の某学部長のKさんに、あらかじめ一言連絡してからでないと悪いかな」。というわけで、翌4月3日の朝、Kさんに電話したら「私、3月31日でやめました。ですからご配慮無用です。お受けにならないのは賢明な選択かもしれません」。
その日にJ大学へ行って「特任教授なみの低賃金で正教授として働かされるような低賃金労働であることを昨日初めて知った。失礼である」と、カッコいい啖呵を切って、雇用契約を結ばないと通告してきた。年金生活者への「男の花道」である。勤労者生活よ、さようなら。高崎の桜はまだ七分咲きで、花吹雪にはまだ間があったのが残念である……。
帰りがけにKさんの研究室に寄ると、画家であるご亭主が応援に駆けつけて研究室撤去のための整理をしていた。KさんがJ大学に学部長としてやってきて、たった1年で辞めるに至った、学部と理事会と学外有力者が入り乱れた伏魔殿のような内紛劇のあらましを聞いた。Kさんとご亭主と私の3人は、やがて場所を駅前の料理店に移して盛りあがった。Kさんと私は酒が飲めずウーロン茶を手に、ご亭主だけがビールを飲みつつ、気炎をあげた。ご夫婦はあと数日かけて研究室とアパートをかたづけ、熱海の邸宅にお帰りになるとか。
東京へ帰るガランとした電車の中で漱石の『坊ちゃん』を思い出した。たった1日で辞令をつき返したのだから、今回は、坊ちゃんよりオレのほうが無鉄砲だったな。
というわけで、この『ジャワ追憶』にのめりこむ以外にやることがなくなってしまったのである。
7.楽しいヴァーナプラスタ
景気がふつふつと煮えたぎっている今のインドではなく、バラモンの時代のインド人は人間の一生を4つの段階に分けたそうだ。それをアーシュラムとよんだ。ブラーマチャリヤ(学生期)、ガールハスティヤ(家住期)、ヴァーナプラスタ(林住期)、サムニャーサ(遊行期)に分けた。古代インド人はダルマ(宗教的義務)とアルタ(家産)とカーマ(性愛)を人生の最大事としていたそうである。この3つの大切を、時期を分けてすべて達成しようという欲ばった人生計画といえる。
よく学び、金と色をとことん追求し、一転、思索にうち込み、やがて飄々と流れてゆく。こんな素敵な人生の実現は至難の業である。しかし、せめて気分だけでもと、1992年の夏、定年を10年前倒しにしてもらって、ジャカルタ―メルボルン―東京を行き来しながら、「私の林住期」を始めた。
メルボルンはいい街だった。町には路面電車が走っていた。籍をおいたモナシュ大学は市街から車まで20-30分のところにあった。大学には連れ合いが付き添ってきてくれた。初日にスーパーバイザー(指導教員)の部屋を訪ねて話し込んでいたら、インドネシア研究では知る人ぞ知るハーバード・フィ−ス教授が現れて、「日本から来ると聞いていたジャーナリスはあなたでしたか」。インドネシア研究の関係者10人ほどで芝生の上に輪になって昼飯を食った。そのとき、誰かが「住むのなら海の見えるセントキルダ・ビーチがしゃれている」と教えてくれた。

アパートの窓から見えたセントキルダ・ビーチの夏
そういうわけで、窓から海の見えるセントキルダ・ビーチにアパートを借りた。メルボルンは気候のいいところである。日本はのべつ雨が降っている。春雨、五月雨、夕立、秋雨、時雨、雪。ジメジメした国だ。メルボルンはカラッとしていた。私の大学の同級生はメルボルン暮らしが永く、すっかりこの気候が気に入って、定年退職後もメルボルンで暮らしている。
メルボルンはのんびりした町だった。カリフォルニア大学バークレー校前の繁華街にたむろする乞食は太い腕をぬっと突き出して
“Spare change” と叫んだが、メルボルンの同業者は “Excuse
me” から始めた。コインランドリーから選択袋を担いでアパートに帰ってゆく道で、すれ違ったオヤジさんから “How’s your washing
today?” と声をかけられた。中古車を買いに行ったら、8年も前の日本車が1万オーストラリア・ドルもした。「高いなあ」といったら、セールスの人が「確かに。車は高いが、家は安いよ」と教えてくれた。その車を3年使って、日本に帰るとき、同じ中古屋に持っていったら、5千ドルで買い戻してくれた。車も安かったことになる。
論文の方はゆったりとしたペースで進んだ。「いま家が安いから1軒買ったらどう? 運がよければ日本に帰るころには値上がりしていますよ」というのが、私のスーパーバイザーの最初のアドバイスだった。大学の図書館に収められている本や論文から取材してストーリーを組み立てる作業はそれほど難しくなかった。取材相手はいつでも図書館の決まった場所で待っていてくれた。
やがて、作業が順調に進むようになってくると、スーパーバイザーと副スーパーバイザイーが「せっかくオーストラリアに来て、勉強ばかりしていてもつまらないから」と、教員仲間の家族ぐるみのピクニックだの、ブッシュ・ウォーキング、キャンピング、映画、観劇などに誘ってくれた。
晩学事始。こんなに楽しいとは思ってもみなかった。
8 グリヤ・ワルタワン
1993年3月から翌1994年の半ばごろまでモナシュ大学があるオーストラリア・メルボルンの海岸、セントキルダ・ビーチのアパートに住み、論文の粗筋を考えた。そろそろジャカルタに移ってフィールドワークを始めようとしていた1994年8月1日夕方、大学からセントキルダのアパートに帰ると、ジャカルタで住む家が見つかったと、友人のアトマクスマからファックスが入っていた。
ヤスオ。
コンプレックスPWIのわが家から20メートルほどのところにある家を貸してもいいとの申し出を受けた。その家はスリ(アトマクスマの妻)の弟で、医師のウマールが数ヵ月前まで借家住まいしていたものだ。豪華な家ではないが十分な広さがあり、また、住み心地もまんざらではないだろう。貸家には電話がついている。また、希望すれば家具付きで提供してくれるそうだ。4寝室で、広い食事・居間兼用のスペースがある。1部屋はお手伝い用の部屋に使える。家具つきにした場合、家賃は少し高くなる。大家に台所とバスルームの改造、3寝室のうち2つにベッドを入れ、さらに1部屋に机や本箱を入れて書斎にし、メインベッドルームに冷房機をつけ、冷蔵庫、台所用品、テレビを入れてくれるかどうかたずねた。大家の計算では、改造し家具付きにした場合の年間家賃は850万ルピア(米ドル換算で4千ドル)だそうだ。大家が改造や家具を入れる都合があるので至急この家を借りるかどうか連絡を乞う。また、君がジャカルタに到着する正確な日付を知らせてくれ。おっと、忘れるところだったが、この家には深い井戸があり、ポンプで水を汲み上げている。昨夜電話したが、留守だった。
アトマクスマ
悪くなさそうな家に思えた。その夜、家具つきで1年間の賃貸契約ができるようとりはからってほしいとアトマクスマに電話した。
コンプレックスPWIはまたの名をグリヤ・ワルタワン(griya wartawan、新聞記者住宅)という。ジャカルタの新聞記者たちがまとまって住んでいる団地「新聞記者村」だった。PWIはスハルト政権によって公認されていた唯一の記者協会、インドネシア・ジャーナリスト協会(Persatuan Wartawan Indonesia)の略称だった。この新聞記者団地は東ジャカルタ地区のチピナン・ムアラにあった。ジャカルタの中心部、たとえばアトマクスマが校長を務め、ジャーナリスト志望の大学卒業生を対象に大学院レベルのジャーナリスト職業教育を行う記者養成所ルンバガ・ペルス・ドクトル・ストモ(Lembaga Pers Dr Soetomo、LPDS)が入っているクボン・シリの新聞評議会ビルまでタクシーで朝夕のラッシュ時で1時間ほど、日中の車の流れが比較的スムーズな時間帯なら30分ほどの距離の場所にあった。

グリヤ・ワルタワン入口
新聞記者村の中にあり、家具つきで、なおかつアトマクスマの家から20メートルのところにある、というのが第一の魅力だった。
アトマクスマは、かつての日刊紙『インドネシア・ラヤ』の編集幹部トシテ、モフタル・ルビスと一緒に働いていた。1974年1月15日の田中角栄首相のジャカルタ訪問のさいに起きた反日暴動「マラリ事件」で『インドネシア・ラヤ』が政府によってとりつぶされたあとはメディア・ウオッチャーとして、スハルト時代の政府とメディア関係をその初期から終末まで体験・観察してきた人である。いわば、現代インドネシア新聞史の生き証人の一人だった。そしてこのインドネシア新聞紙の生き証人は、スハルト後の新聞自由化の時代になると、乞われてインドネシア新聞評議会の議長に推され、ジャーナリズムへの貢献でマグサイサイ賞をもらった。『インドネシア・ラヤ』という新聞は、主筆だったモフタル・ルビスと編集局長だったアトマクスマ・アストラアトマジャの2人のマグサイサイ賞受賞ジャーナリストを輩出した。この話もおいおいと……。
つぎに電話つき。携帯電話の普及で世界中のどこからでも話が通じる時代の今となっては信じられないだろうが、1990年代の前半、仕事でジャカルタに来て月額30-40万円の家賃の家に住んでいる日本人の会社員、あるいは公務員、半公務員にとってはなんでもない電話が、私費でジャカルタにフィールドワークで来る学生にとっては、ちょっとした問題なのであった。モナシュ大学の同僚学生は「電話つきの家か。ラッキーだったな」と祝福してくれた。そのころモナシュ大学にまねかれ、ジャワ語の辞書を編纂していたインドネシア大学の先生でさえ、ジャカルタ郊外の彼の大学の近くにある自宅では永らく電話設置の順番待ちが続き、いまだに電話が無い状態だった。
9 ジャラン・レダクシ
私が住んだグリヤ・ワルタワンは「新聞記者団地」だけあって、団地内の通りにすべて新聞ゆかりの名前がつけられていた。団地前の大通りがジャラン・メディア・マッサ(マス・メディア通り)。団地内にはジャラン・レダクシ(編集局員通り)、ジャラン・カントール・ブリタ(通信社通り)、ジャラン・タジュック・ルンチャナ(社説通り)、ジャラン・コレスポンデン(特派員通り)などなど。私が住んだのはジャラン・レダクシだった。

新聞記者団地の新住民になった私は、身元保証人のアトマクスマに連れられて、団地管理組合長を訪れ、住人の仲間入りを承諾してもらった。この組合長さんは退職した新聞記者で、クリス(ジャワの短剣)の研究家だった。クリスは不思議な魔力を持つと信じられている儀礼用の短剣である。この組合長さんは、日本人が日本刀にたいして同じような気持ちを持っているのではないかと、私にあれこれ質問するのであった。そのあたりに暗い私は、「詳しい話はまたの機会に」と組合長さんのお宅をそうそうに辞した。
さて、実際にジャカルタに来てこの家を大家と1年間の賃貸契約を結ぼうとしたとき、大家は家賃を850万ルピアから1,000万ルピアに値上げした。臆面もないバーゲニングである。契約に立ち合ってくれたアトマクスマとスリが、対抗措置の応援をやってくれたが、ききめはなかった。大家の言い分では、値上げの理由は家具つきにするのに費用がかさみ、当初の予算をかなりこえてしまったからだという。
大家が家具とよんだしろものが、いま思い出してもおかしい。たしかに、約束通り、電気冷蔵庫、テレビ、冷房機、たんす、本箱、書斎用のデスク、応接セット、ダイニングテーブルと椅子、ベッド、調理器具、食器などが運びこまれていた。
テレビはこの家に引っ越して3日目に、映像も音声も出なくなった。冷蔵庫は冷凍室のついていない小型の古いもので、ほとんど使い物になりそうになかった。冷房機は効目のわりにはモーター音が大きくて騒々しいうえ、使った翌朝から喉がいがらっぽくなり咳が止らなくなった。このがらくた同然の冷房機の内部にカビがはえ、冷気よりもカビを室内にまき散らすだけの道具になっているのだろうと考え、使うのをやめた。
しかし、もっとも“感動的”だった「家具」は、来客用のベッドルームに入れてくれた、正確に表現すると大型の「かつては姿見つき化粧台だった」しなもの。幅一メートル、高さ二メートルのサイズだったが、全体が駄菓子のようにピンクの塗料で塗られ、それが古くなってあちこちで剥げている。まことに下品な雰囲気をかもしだしていた。それに驚いたことには、この家具には本来ついているはずの姿見用の鏡がついていなかった。鏡が壊れてなくなってしまった姿見を「家具」として持ちこんだ大家の「神経」に感服した。おそらくはごみ集積場から拾ってきたものだったのだろう。結局、テレビと冷蔵庫、食器類は新しいものを買った。
洗濯機を買おうかと、お手伝いさんに意見を求めたら、いらないという返事だった。電気器具店では洗濯機も勧められた。いらないと断ると、「お手伝いに洗わせた方が安上がりでしょうね」といった。ジャカルタのお手伝いさんはそのような存在として見られていた。

ジャラン・レダクシのかつての仮寓
この家にはバスルームが3ヵ所あった。バスルームといっても、便器と、水槽をそなえたタイル張りの狭い空間だ。給湯設備なく、湯舟なく、汗をかいたら体中に石鹸をぬりたくって水槽の水をくんで流すだけ。便器は西洋式の腰掛タイプだったが、壁にはトイレット・ロールを取り付けるところがなく、排便後はお尻を水槽からくんだ水で左手を使って洗う方式だった。
5つ星のホテルのレストランでのディナーであれ、コンプレックスPWIのわが家での夕食であれ、それを作り、運んでくる人はみんな左手で排便後の始末をつけているわけだから、いまさら自分一人が紙を使ってもはじまるまいと、ジャカルタ滞在中は紙なしですませた。東京から視察にやってきた私のつれあいも紙なしですませた。ひょんなことで私の借家に数日間泊まることになった、ハノイのジャーナリスト2人も紙なしですませた。私の家にしばらく滞在した私のスパーバイザーもそうだった。まあ、この方は、以前、ジャワで長らくにわたってフィールド調査をした経験があったから、どうということもなかったろう。
最初は指先のヌルッとした感触が気になったが、すぐになれた。インドネシア人の多くは右手の指で食物をつまんで口に運び、かつて食物だったものが体外に排泄されるときは、それを左手の指で始末する。左手の指つかいはすぐ上達したが、右手の指を使って食事する、それも、人前で上品にやってみせるのはなかなかに難しかった。
10 カマール・クチル
いましばらく厠(カマール・クチル)のお話にお付き合い願おう。
下水道がまだ十分整備されていないジャカルタでは、当時、一般民家のトイレは地下浸透式が多かった。多分、今でもそうだろう。水で流した屎尿は地下に導かれ、そこからいずこともなく浸透して行く。バクテリアによる分解や、土の濾過作用に期待しているのである。
日本でも山小屋のトイレにはこの手の地下浸透式が多い。登山ブームで山登りを楽しむ人が増えたので、山の浄化力が追いつかなくなった。いまどきは山の岩清水も安心して飲めない。

ジャカルタ国立博物館で
ジャカルタでも同じだった。トイレからしみ出した汚水が井戸にたまり、あるいは水道管の裂け目から水道水に交じり、台所に循環して行く。この意味で、アトマクスマがファックスに書いていた深い井戸というのは、渇水期にも水が底をつかないという意味と、汚水は濾過され、生々しいままでは届かないというイメージを与えるが、後者の場合、実際上の効果はあまり期待できないだろう。
屎尿を地下に浸透させない工夫としては、川や池の上にトイレをつくり、終末処理を魚につとめさせる文字通り川屋の水上式便所や、下で飼っている豚が排泄物を始末してくれる陸上高床式便所などの工夫がある。
私の知人のインドネシア人の中には、水上式トイレを理由に淡水魚を食べない神経質な人もいた。
豚とトイレの関係については、史馬遷が史記に書いている。漢の高祖の妃、呂大后は後継者争いのすえ高祖の側室戚姫を捕らえて、彼女の手足を切断し、目をくりぬき、耳を焼き、薬をつかって声が出せなくしたうえで戚姫を便所にいれて「人ブタ」とよんだという。中国の公厠を覗いたことのある人には、これがどんなに悲惨なことか想像できるだろう。さすがにオリンピック開催をひかえ、北京では街のトイレの整備が進んでいるそうである。
陸上高床式の場合、インドネシアでは豚が「用済みの尻をきれいになめてくれるという」1990年代に出版されていたされていた大槻重之の『インドネシア百科』に書いてあった。真偽については知らない。しかしありそうな話だとは思った。
かつてペルーのアンデス山中をトレッキングしていたとき、ある日、私は山中の小さな集落でイノシシように精悍な豚と野犬が激しく格闘をしているのを目撃したことがある。「豚の方が強い。かけてもいい」と、私の隣で同じように観戦していた同じトレッキング隊のニューヨークから来た男が即座に断言した。というのも、彼は以前、ある航空会社のリマ支社で働いたことがあり、今回と同じようにアンデス山中で豚と犬の一騎打ちを目撃したことがあったからだ。彼によると、勝負は終始豚の方が優勢で、追い詰められた犬は最後に身体を震わせながら悲鳴をあげ、恐怖のあまり失禁してしまった。犬が逃げ去ったあと、豚は戦利品である脱糞されたばかりの犬の糞を悠然と食べたというのである。したがって、豚が尻をなめてくれるという情報をにわかに否定もしがたかった。
というわけで、インドネシアでは人糞は汲み取り時代の日本と違って肥やしに使っていないようであった。肥やしにしているのはもっぱら家畜の糞で、ププック・カンダン(pupuk
kandang、畜舎の肥やし)という言葉がある。

緑陰のジャラン・オピニ
さて、深い井戸はあったが、前住者がこの家を去り私が住みつくまで間に汲み上げ用の電動ポンプが盗まれていた。大家によると汲み上げ用ポンプの盗難はジャカルタの住宅街ではポピュラーな盗難の一つで、やがてまもなくアトマクスマも「うちのポンプも盗まれちゃった」と嘆くことになった。しかし、公営水道のパイプも入っていて、それが使えるのでしばらくはこの井戸のことを忘れていたが、やがて水道の水が黄河の水を交ぜたような色になり、大家に新しいポンプをつけてもらった。しかし、このポンプもまた、1ヵ月余りで不調におちいり、新しいものと交換しなければならなくなった。
11 カチョア
新聞記者団地の借家の天井からはときどき動物の運動会のような音が響いた。ジャカルタ勤務をした友人の家では天井を突き破って猫が落ちてきたことがあったそうだ。メルボルンの知人の家では、ポッサムとよばれる小動物が落ちてきたという。私の借家では天井から動物が落ちてくることはなかったが、ある日の深夜、4,5匹のネズミが食卓の上でバナナをかじっているのを目撃した。
市場ではバナナは本単位でなく、房単位で売っていた。バナナにもいろいろな種類があって、ピサン・ゴレン(バナナ・フリッター)などに使う調理用バナナもあれば、生食用のバナナもあった。木で熟したバナナはうまかったが、なれとは恐ろしいもので、そのうちバナナなど食べたくもなくなった。
ものの本によるとバナナは木ではなくて、草だそうだ。花を咲かせ実をつけると枯れてしまう。インドネシアの学者仲間では、博士論文を書いたのを最後に、あとこれといった作品を発表できないでいる学者を「ポホン・ピサン」(バナナの木)とあざけっていた。不肖私もそのバナナの木学者の1人になってしまった。
さて、ネズミの話にもどるが、お手伝いさんのハルティニの夫、スワルトがたまたま大工さんで、彼が一日かけて家中の穴という穴を、無料奉仕ですべてつぶしてくれた。それ以後ネズミは出なくなった。
ハエ、ゴキブリ、蚊はいたるところにいた。夕暮どきと就寝前の2回、ハルティニが家中にジャカルタで当時最もポピュラーな殺虫剤であったバイエル社のバイゴンをたっぷりと撒く。翌朝目を覚ますとベッドのそばでゴキブリが仰向けになってくたばっていた。脚をこまかく震わせながら断末魔の様子である。棒の先でその臨終まぎわのゴキブリを正常な姿勢にもどしてやるとヨタヨタと歩き出すのだが、すぐひっくり返ってまた仰向けになってしまう。ゴキブリが殺虫剤で死ぬときは必ず仰向けになるということをこのとき初めて知ったが、ゴキブリまで死んでゆくこの殺虫剤の効目も恐怖だった。毎朝、ハルティニと顔をあわせると、
「ハルティニ、ゴキブリだ」
と不機嫌につげるのが日課になった。ハルティニはほいほいと私の寝室に入り、ゴキブリ数匹を素手でつかみ、なんでこんなものが怖いのかとばかり、
「オー、カチョア(kacoa、ゴキブリ)。ハッハッハッ!」
と大笑するのであった。
ジャカルタ滞在中、アトマクスマの末っ子のトリがデング熱にかかって入院した。病院の医師は「今年はコンプレックスPWIでデング熱の発生が多いなあ。あなたの息子さんで四人目だ」とアトマクスマに語った。殺虫剤でおかしくなるか、それとも虫が原因で病気かかるか、いずれにせよ危険はつきまとった。
幸い病気にはならなかったが、日本に帰ってから愛用のニコンを点検に出したら、
「中がカビだらけです。水中に落としましたか」
とたずねられた。さすがに瘴癘の地である。ニコンの被害程度ですんでよかった。後にアトマクスマは肺がんを疑われ、入院して精密検査を受けたところ、肺にカビが生えていたそうである。

新聞記者団地の大通り Jalan Media Massa
周辺の土地よりやや高台になっていた新聞記者団地では、雨季の本格的洪水による家屋浸水の恐れはなかった。しかし、家は雨漏りがした。雨季になるとハルティニが「ボチョール(雨漏りだ)」「バンジール(洪水だ)」と叫びながらモップとバケツを持って家の中を走り回った。私の借家が特にお粗末だから雨漏りがしたわけではない。当時の大統領スハルトの私邸もある屋敷街メンテンに住んでいた知人の借家は、大家が元インドネシア副大統領という邸宅だったが、やはり雨漏りがした。ある日の夕刻、その知人といっしょに外出し、激しい夕立のあと夜更けになって邸宅に帰ってきたら、なぜか豪邸の明りがすべて消え、家の中は真っ暗だった。
出てきたお手伝いさんに「どうした」と聞くと、その第一声が「怖かった」と震え声。大雨の最中、ババーンという大音響がして停電になったという。知人が彼の寝室に入ってみると、天井の蛍光灯が爆発したらしく、砕けたガラスが彼のベッドの上に降り注いでいた。この出来事はジャカルタに赴任してまもない彼にはちょっとしたショックだったらしく、その夜、彼は「お手伝いたちにはかわいそうだが」とつぶやきながら、暗い豪邸から1人ホテルに避難した。
12 コルシ
ジャカルタのグリヤ・ワルタワンあるいはコンプレックスPWIこと「新聞記者村」は1970年代の初めに造成された。
「村」の建設をめぐってはいわくがある。コンプレックスPWIは政府のジャーナリスト宣撫策のひとつだったという説がそれだ。この説をとなえたのが、かつて日刊紙『ハリアン・カミ』編集長だったノノ・アンワール・マカリムである。
カリフォルニア大学から出版された『インドネシアにおける政治権力とコミュニケーションズ』(1978)に収められた彼の論文「インドネシアのプレス―ある編集者の見解」の中で、彼は次のように言っている。
インドネシアの新聞記者は東南アジアの同業者の中でも薄給の部類にはいり、特権による生活上の恩恵をあてにしている。ジャカルタ知事が造成した宅地をインドネシア・ジャーナリスト協会(PWI)のために用意し、中央政府が住宅普及のパイロット・プロジェクとして新聞記者村建設を後押しし、国有銀行が記者たちのために低金利のローンを提供した。
当時ジャーナリスト協会のジャカルタ支部財務部長としてこのプロジェクトの中心にいたアトマクスマにノノ・アンワル・マカリムの見方について感想を聞いたところ、いつもは温顔の彼も、さすがにムッとした表情になって、
「住宅パイロット・プロジェクトの話を聞き込んで、正規の手続を経て協会として取り組んだ。ローンに対しても正当な金利をきちんと支払った」
と反論した。

韓国では1980年代の全斗煥大統領の政権下で、ジャーナリストのための持ち家促進資金の制度が創られたことがある。日本では、新聞社が国有地の払い下げを受け、壮大な社屋を建てている。これに対して言論機関が国家権力から恩恵を受けているという視点を強調する批判も可能であるし、一方、正当な土地取引が行われたが、それがたまたま政府と新聞社の間であったにすぎないという説明も可能である。
ノノ・アンワル・マカリムはたまたま前者の視点からコンプレックスPWIの造成過程を外国人向けに説明したにすぎないのかもしれない。こうしたジャーナリズムと国家の関係は理論上は大きな問題だが、住宅難のジャカルタに生きる生活者としてのジャーナリストにとってはそんなことにこだわるよりも、とにかく家を手にいれる機会の方が重要だった。週刊誌『テンポ』が編集した現代インドネシア人名事典(1986年刊)をのぞくと、ノノ・アンワル・マカリムの自宅住所もまたこの「新聞記者村」になっていた。
新聞記者団地が造成当初に建てられた住宅は40平方メートル程度の小さな納戸風の質素なものだった。私が住んだころでも新聞記者村の中に数軒残っていた。それはマスコミと権力のコルシ(kolusi、癒着)をうんぬんするほどもない住宅だった。しかし、ここに住宅を手に入れたジャーナリストたちは、やがて、この国の経済の発展と各人の幸運の程度に比例して、あるものは村の外に土地を買い豪壮な邸宅を建てて、村を出て行った。残ったものは村を出ていった仲間の跡地を買い取って敷地を広げ、しゃれた住宅を新築した。
アトマクスマも、隣家の跡地を買い取り、家を新築し、広くなった庭にランブータンの木とドリアンの木を植えた。ドリアンの木は私の滞在中には実をつけることはなかったが、ランブータンは篭にいれられアトマクスマから届けられた。市販のランブータンより小粒だったが、甘みは強かった。
アトマスクスマが勤めていた新聞『インドネシア・ラヤ』が1974年の田中角栄ジャカルタ訪問時の暴動報道を理由に政府によってつぶされた。アトマクスマ本人も、ペルソナ・ノングラータとしてインドネシアのジャーナリズムの世界から事実上のパージを受けた。以後、彼はジャカルタの米国大使館の広報部門で働いてきた。したがって、彼の家の拡張はアメリカ政府から支払われた給与によるもので、インドネシアのジャーナリズムの経済的な成功とは直接の関係はなかった。
13 ウントゥン
ジャカルタに駐在する外国人の豪邸に比べると、陋屋に近い、いろいろと難のある新聞記者村の借家ではあった。しかし、都会を遠く離れた辺地をフィールドに定めて住みつき、そこで何年も暮らさなければならない人類学者などの住いにくらべれば、とほうもなく清潔で快適だった。ともあれジャカルタにたどりつけた。ここまでくれば、博士論文はもう7割がた完成したも同然だ。ウントゥン―幸運だった。そう考えることにし、そのとおり納得した。

アトマクスマ邸の庭で
スハルト個人支配体制絶頂期の1990年代前半、オーストラリアの大学では、インドネシアの政治が絡むテーマで博士論文を書こうとする学生にとって、インドネシアの調査ビザを取るのは博士号をとるより難しい、といわれていた。ビザを申請したものの待たされるばかりでいっこうに発行させず、問い合わせてもらちがあかず、そうこうするうちに博士課程の奨学金期限が切れてしまった学生が何人もいた。なにも心当たりがないのに、ビザ発行を拒否された学生もいた。最初の調査ビザはすんなりもらえたが、二度目のビザを拒否され、以後、いくらがんばってもインドネシアの調査ビザがもらえなくなった研究者もいた。人類学者のこの人は、フィールドをマレーシアに変更した。
メルボルンのインドネシア領事がモナシュ大学にやってきて、インドネシア研究がテーマの学生たちと懇談したことがある。
「インドネシアに何かご要望は?」
と、その外交官がいったとき、即座に出た発言が、
"Get me a visa!"(「ビザを発給して」)だった。
そういうわけで、1993年の3月にモナシュ大学アジア研究科の博士課程に学籍登録をすませて2ヵ月たった同年5月、インドネシア科学院(LIPI)を通して調査ビザの申請をした。論文のテーマは「インドネシアの新聞と民主化」だった。そのままの題目で申請するのはちょっと考え物だった。だれが言い出したのかは不明だが、そのころのインドネシア政治調査の要諦は「ビー・オネスト・バット・ビヘイブ・ディプロマティカリー」(正直であれ、ただし如才なくたちまわれ)だった。
ビザ申請用紙には調査テーマを “Media and Development”とした。メディアは新聞の言いかえ。ディベロプメントは民主化(democratization)を政治発展(political development) といいかえ、さらにそこからポリティカルをけずった。そうすると「メディアと開発」のベールができあがった。
ビザ申請にあたっては身元引受人が必要だった。身元引受人はインドネシアの国立の機関に所属する人に限るといわれた。身元引受人は引き受けた人物の研究内容についても責任を持つことが求められていた。というわけで、身元保証人になってくれる人物を探すのが大変だった。私の場合、友人の友人がインドネシア科学院の政治学者で、その人に頼み込んで身元引受人になってもらった。
ビザ申請からビザ取得まで、結局、1年かかった。モナシュ大学のスーパーバイザーや友人は、「ビザなしでも2ヵ月はインドネシアに滞在できるので、2ヵ月に1度シンガポールに出て、また、ジャカルタに戻ればいい。そうやって、通算2年ジャカルタでフィールドワークをこなした学生がいる」という意見と、「ビザを申請して一度拒否されると、あと何度申請してもビザは取れない。とはいえ、やはり、正式のビザを取ったほうがいい」という意見に割れた。

そうこうしているうちにビザ申請から1年がたった。メルボルンからジャカルタに飛び、インドネシア科学院をたずねてビザの督促をした。その足で、アトマクスマが当時校長をつとめていたジャーナリスト学校のドクトル・ストモ学院(LPDS)をたずねたら、そこでアトマクスマの前任の校長で、そのころハノイ大使に転出していた元ジャーナリストに再会した。かれにビザの話をしたところ、「聞いてみてあげる」とのこと。
それから、数日後に滞在中のホテルにインドネシア科学院から「ビザが出た。取りにきてください」と案内があった。コネクシ(コネクション)が劇的にきいたのか、もともとビザ発行の時期にきていたのかは不明のままであるが、ともあれ、幸運であったことには間違いなかった。
|




















