
1
サンジェルマン・デ・プレ教会のミサ
2019年12月24日。午後4時ごろオルセー美術館が定刻より早く門を閉めた。クリスマス・イブの習いである。
セーヌ川左岸の通りをシテ島の方角へぶらぶら歩く。いつもなら川岸に店を開いている絵や本、お土産の屋台のほとんどが閉じている。それほど寒くはなく、川風も冷たくはない。とはいえ、なんとなくさびしさを感じさせられる。
国立高等美術学校の角を右折してさらに歩き続けると、ほどなくサンジェルマン・デ・プレ教会に着く。パリで最も古い、ロマネスク様式のカトリック教会である。教会の周りの歩道にクリスマス・マーケットがあった。いくつかの店が開いている。
教会と道路を挟んで向かい側のカフェ「ドゥ・マゴ」に入って、少々早めの夕飯、というか遅めのランチを注文する。24日はルーブル美術館をはじめパリの多くの美術館の休館日にあたる火曜日なので、観光客が休館日でないオルセーに集中し、館内のカフェには長い行列ができていてくいっぱぐれた。
 
料理が運ばれて来るのを待ちながら、かれこれ10年以上ご無沙汰している2体のマゴ人形を見上げる。店内の柱の上の方に神棚風に鎮座している。ドゥ・マゴは名高い歴史的カフェなのだが、食事はたいしてうまくない。肉料理に添えられたパンも食後のコーヒーもパリの水準から抜きんでたものではない。代金だけが水準以上である。観光客にとっては、ドゥ・マゴの椅子に座ったというのが値打ちなのだ。ドゥ・マゴといっても渋谷のアレではないぜ、サンジェルマンの本店だぜ、というわけだ。
ドゥ・マゴを出て、道路を渡り、サンジェルマン・デ・プレ教会に入るとクリスマス・イブのミサが進行していた。聖職者がキリストをたたえ、この世の平和をねがい、クリスマスの聖歌を歌い、その歌声に参拝者が時々声を合わせた。日本の仏教のお経と同じで、フランスの聖職者が語るフランス語のクリスマス・メッセージは皆目理解できないが、いい雰囲気だった。日本のお坊さんの読経を聞けば去って行った人のあの世での平穏が思われ、サンジェルマンの教会で聖歌を聞くと――オルガンの響きが良かったせいもあって――クリスマスの気分にひたり心が清められる心地がする。パブロフの条件反射のようなものだ。
やがて、参拝者全員が椅子から立ち上がり、お互いに抱擁しあった。白装束の少年3人が大きな蝋燭を手に現れ、祭壇に向かって進んだ。キャンドルライト・サービスはクリスマス・イブの定番である。それは救済の光なのである。
トランプ氏が米国と世界を洗濯機のようにかき混ぜた。フランスでは2018年から始まった黄色いジャケット運動以来、2019年に入ってもマクロン氏の人気が衰えつづけた。ドイツではメルケル氏の引退が決まった。すったもんだのあげくイギリスは総選挙でEU離脱問題に一応の決着をつけた。香港では若者たちが中国の抑圧に抗議するデモを繰り広げた。オーストラリアでは例年にない山火事が広がっている。北朝鮮は貧困の中でなおツッパリ続ける。日韓関係は膠着。日本国内では「桜を見る会」「カジノ」などの代議士をめぐる醜聞が相次いだ。とはいうものの、日本の若者も世間も取り立てて怒り狂っているようには見えない。これは良いことなのだろうか?
2 シャンゼリゼ
シャンゼリゼ大通りは凱旋門があるシャルル・ドゴール(旧エトワール)広場とオベリスクが立つコンコルド広場の間を一直線に走っている。その大通りのマロニエの並木がクリスマスのころイルミネーションで輝く。
まず、凱旋門方向をながめると、こんな具合である。

ふりかえってオベリスクの方角に向かえば、こんなふうである。

シャンゼリゼ大通りは今年、赤のイルミネーションで決めている。
一方、シャンゼリゼ大通りと接続するモンテーニュ大通りは金色のイルミネーションだ。

シャンゼリゼもモンテーニュもパリを代表する通りである。シャンゼリゼにはルイ・ヴィトン、カルティエ、ロンシャン、それにディオール。モンテーニュ大通りにはグッチ、シャネル、ジヴァンシー、ニナ・リッチ。
オー・シャンゼリゼという歌がかつて日本でも流行した。♪晴れても降っても、昼も夜も、シャンゼリゼには望むものすべてがある♪
大意このような歌詞は、ヴェブレンの『有閑階級の理論』を思い出させる。名声の基礎は金銭的な実力であり、金銭的な実力を示す手段が衒示的消費である。要するに体面と見栄の誇示のための無駄遣いである。私は古いセイコーの鉄道時計を愛用している。今でも正確に動く。その私がシャンゼリゼでカルティエの100万円の腕時計を買えば――現実には不可能で、理屈上の話にすぎないが――それが衒示的消費である。
シャンゼリゼ大通りやモンテーニュ大通りにやってきて衒示敵消費を楽しむのは中程度以下の金持ちで、大金持ちは店頭には姿を見せない。店員が商品をもってその邸宅へお伺いするのだ、とパリに詳しい人から聞いた。
以前はこの時期になるとシャンゼリゼ大通りの両側に、貧民でも買い物が楽しめるクリスマス・マーケットが並んだそうだが、2018年から姿を消している。聞くところによると、パリ市当局がクリスマス・マーケットのオーガナイザーに道路の使用許可を与えなくなったからだという。オーガナイザーは大統領府の肝いりで、ルーブル向かいのテュイルリー公園の一角へ出店者を率いて移動し、クリスマス・マーケットを開いている。
3 セーヌ
セーヌ川はパリの中心を流れている。沢山の橋がかけられている。シテ島を中継して両岸をつなぐ橋だけでも「ポン・ヌフ」をはじめ4本ある。
ライトアップされたポン・ヌフが夜目にも著く見えてきた。右岸からながめるとシテ島側の橋のたもとにセーヌの遊覧船の船着き場が見える。気のせいかセーヌが水量を増しているようにも見える。

ポン・ヌフは新しい橋という意味だが、この橋は現存するパリ最古の橋だ。16世紀後半に着工、17世紀初頭に完成した。以後、修理を重ねたが、基本的な構造は当初のままだ。
東京にも「新橋」がある。JR新橋駅の汐留側に立ち食い蕎麦のスタンドがあった。その名を「ポン・ヌフ」と言った。名前と実態のズレが愉快なので、一度立ち寄って食ってみたいと思っているうちに、いつのまにか店は閉じられていた。
セーヌはフランスの平野部をゆったりと流れる穏やかな川なのだが、ときどき氾濫することがある。最近では、2018年1月。冬の大雨でセーヌが増水して流れが堤防からあふれた。花の都がベニスのような水の都になった。川岸にあるルーブル美術館は低層階を閉じ、美術品を避難させた。
セーヌ川はまた汚染された都市河川でもあった。東京の隅田川と同じ。水質浄化に努めた結果、セーヌ川、隅田川とも現在では改善されてきている。2024年の夏のオリンピックはパリで開催される。パリ市当局はトライアスロンの水泳をセーヌ川で行いたいとしている。そのために、さらなる水質浄化を進める予定だ。東京オリンピックでトライアスロンの水泳が行われるお台場のように、すれすれの水質にやきもきすることになるだろう。

ポン・ヌフの上流に何本かの橋が見える。アポリネールが「ミラボー橋の下をセーヌ河が流れ われらの恋が流れる……日も暮れよ、鐘も鳴れ 月日は流れ、わたしは残る」(堀口大學訳)と歌ったミラボー橋はこの中にはない。ミラボー橋はずっと下流にかかる橋で、観光客があまり行かないところだ。
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
アポリネールの「ミラボー橋」には曲がつけられ、シャンソンとして歌い継がれてきた。この部分はそのさわりである。
詩人ギョーム・アポリネールは画家マリー・ローランサンと恋中になり、ローランサンが住んでいたミラボー橋近くに引っ越した。芸術家同士の恋は成就すれば物語性に乏しくなる。胸を打つのは悲恋である。やがて二人は別れ、それぞれ違う人と結婚した。アポリネールは37歳で死んだ。ローランサンは72歳まで生きた。
ある程の菊投げ入れよ棺の中 漱石
ローランサンの遺言どおりに、棺の中のローランサンの胸にはアポリネールからの恋文が添えられていた、といわれている。ローランサンは自分が描いたナイーヴでセンチメンタルな絵の娘のように人生を送り、死んだ。
4 クリスマス・セール
 オルセー美術館でたまたま企画展『オペラ座のドガ』を開催していた。ドガはオペラ座に通って、踊り子の様々な姿を描いた。この作品「エトワール」は、中学校か高等学校の西洋美術史の教科書で見た記憶がある。可憐な絵、という印象だった。 オルセー美術館でたまたま企画展『オペラ座のドガ』を開催していた。ドガはオペラ座に通って、踊り子の様々な姿を描いた。この作品「エトワール」は、中学校か高等学校の西洋美術史の教科書で見た記憶がある。可憐な絵、という印象だった。
大人になって――といっても相当の年配者になって、この昔懐かしい絵のオリジナルを初めて見た。そしてはじめて知った。
この絵をよく見ると左上の幕のあたりに黒っぽい人影が見える。学校の教科書に掲載されていた写真では見落としていた部分だ。
『オペラ座のドガ』展の解説によると、この黒い服を着た人物は男性で、この踊り子のパトロンだという。
エドガー・ドガがこの絵を制作した1876年ごろ、オペラ座はパトロン希望者の裕福な紳士とパトロンをさがす踊り子との出会いの場となっていたそうである。そんなこと、たとえ歴史的背景だとしても、中高校の先生が生徒に念入りに教えることはまずない。
現在のパリにはオペラ座が2つある。ドガが踊り子たちの絵を描いたのはオペラ・ガルニエで、古い方のオペラ座。新しいオペラ座はバスティーユ広場にあるオペラ・バスティーユ。ドガゆかりのオペラ・ガルニエはルーブル美術館からオペラ通りを歩いて突き当りに位置している。

そのオペラ・ガルニエの背面の通りにパリの大手百貨店であるラファイエットとプランタンがある。ラファイエットは3つの建物で構成されている。そのひとつグルメ館をのぞいてみた。クリスマス用のケーキ、ハム、チーズなどを買い求める客で大賑わいだった。
フランスのケーキはおいしそうに見えた。フランスは農業国だから、ノルマンディー地方のチーズはおいしい。ハムもうまいが、日本に持ち込みが禁止されている。ずいぶん前のことだが、フランス政治思想史を専門している先生が、フランスへ行った帰りに、生ハムの片足1本をまるごとスーツケースに忍ばせて持ち帰り、電動のスライサーを買って、当時は豪華絢爛の食品だった生ハムの大盤振る舞いをしてくれた事があった。いまそんなことをしたら大変だ。
ラファイエットの隣のプランタンは、かつて東京・銀座に進出していたが、撤退して今はない。プランタンの本店はのぞかなかったが、ルーブル美術館の地下にあるプランタン・ルーブル店でクリスマス・セールを行っていた。

1年で一番楽しいショッピングの季節である。
とはいうものの、クリスマスイブの24日の宵に、サンジェルマン・デ・プレ教会に詣でたついでに見た教会周辺のクリスマス・マーケットは人影がまばらで、寒々しかった。

ルーアンの大聖堂の写真を撮りに行ったとき、カテドラル前の広場のクリスマス・マーケットをのぞいたが、開店早々の午前中だったせいか、お客さんは少なかった。新宿・花園神社の酉の市などの雑沓とはずいぶんと違う。

5 パリへ
2020年1月16日、米国下院がトランプ大統領の弾劾決議を上院に送った。
東京からパリへ向かったのが2019年12月19日。空港のテレビがCNNの米下院の審議の模様を中継していた。トランプ大統領を弾劾すべきかどうかという議論である。議員が次々に登壇して意見を述べていた。
  
飛行機が飛び立ってもCNNは議会中継を続けていた。飛行機の中でご飯を食べて、あくびをして、一眠りして、目が覚めてもCNNは大統領弾劾の議会ニュースを流していた。画面を見ると、演説が終り、採決を経て、下院の弾劾決議が成立していた。
パリが近くなってきたころ、ペロシ下院議長が当面は弾劾条項を上院に送らないというニュースをCNNが流した。上院の共和党議員の態度を慎重に測っていたのだろうが、下院決議から上院送付まで4週間かかった。
 パリに着いたら交通ストが続いていた。空港から市内まで車が数珠つなぎで、普段なら40分のところ3倍以上の時間がかかった。 パリに着いたら交通ストが続いていた。空港から市内まで車が数珠つなぎで、普段なら40分のところ3倍以上の時間がかかった。
パリの交通ストは1月16日現在なお続いている。ストライキが始まってすでに40日以上がたつ異常事態だ。
詳しいことは不案内だが、年金制度の変更をめぐるマクロン大統領案に、交通労組が恵まれたものがより恵まれ、恵まれていない者はより恵まれなくなる、と激しく反対している。フランスの年金制度は業種によって異なり、マクロン政権は複雑な年金制度を一本化しようとした。
16路線ある地下鉄のうち動いているのは2路線のみ。あとは完全停止か、部分運行。地下鉄入り口のシャッターは閉じられたままだ。
公営バスはまがりなりにも動いている。なかなか来ないバスを辛抱強く待つか、自転車で移動するか、あとは自分の足で歩くしかない。
動いている地下鉄もバスも満員で、スリが横行しているとのうわさが広がっている。EUのスリがパリに大集合しているとささやかれている。
そういう日々がもう40日以上続いている。パリの人は辛抱強い。
2018年から2019年にかけて、フランスで黄色いチョッキ運動が盛り上がった。マクロン政権に対する批判の該当運動だった。その余熱がまだ残っているのだろうか。フランスの労働組合組織率は全業種平均で1割程度と言われている。
日本の労働組織率はフランスより少し高いが、日本では久しく交通ゼネストは発生していない。フランスは面白いところだ。
6 市庁舎
さて、2019年のクリスマス・シーズンのパリのイルミネーションをいくつか紹介してきたが、ついでにパリ市庁舎とエッフェル塔の写真を出しておこう。
パリ市庁舎はパリの観光名所である。昔はここで公開処刑が行われ、見世物が少なかった時代には大勢の見物人が集まった。フランス革命のバスティーユ襲撃時は市庁舎が反王政派の拠点になった。バスティーユ砦のローネー守備隊長はとらえられ、市庁舎に身柄を送られる途中、民衆によって殺された。民衆は守備隊長の首を切り落とし、その頭部を槍の穂先で突き刺し、それを高々と掲げてデモ行進した。

当時の市庁舎の建物は1871年のパリ・コミューンの革命政権の本拠となったが、軍に攻撃されて革命派が火を放ったため焼け落ちた。現在の市庁舎はその後に再建されたものである。
歴史の血なまぐさい舞台になった建物であり、市庁舎をライトアップしている青い光が不気味である。
エッフェル塔はパリの名所で多くの観光客がこの塔に登って下界をながめ、下界からこの塔を見上げて、写真に収める。
エッフェル塔は構造物自体には著作権はないので、日中に塔を撮影してその写真を利用することは問題ない。しかし、最近、エッフェル塔に夜間のイルミネーションを添え、そのデザインを著作権登録したので、夜間のエッフェル塔を撮影して写真を公開するとフランスの著作権法違反で訴えられる可能性があるといわれている。

一方で写真家の中にはエッフェル塔のイルミネーションを撮影してブログで公開し、SNSに載せる程度なら大丈夫だという人もいる。その見解を信じて、クリスマス・シーズンに撮影した夜のエッフェル塔の写真をここに掲載する。
7 赤い風車
パリで泊った宿はモンマルトルにあった。

モンマルトルといえば、後世に名を遺した画家たちが多く暮らしていた街である。ルノワール、ドガ、ゴッホ、ユトリロ、ロートレック、モディリアーニ、ピカソらがかつてここで仕事をしたことがあった。
 モンマルトルはまた歓楽の街でもある。宿泊したホテルは地下鉄のクリシー広場駅近くにあった。ホテル近くのクリシー通りを少し歩くとそれらしいにおいのする界隈にたどり着く。 モンマルトルはまた歓楽の街でもある。宿泊したホテルは地下鉄のクリシー広場駅近くにあった。ホテル近くのクリシー通りを少し歩くとそれらしいにおいのする界隈にたどり着く。
通りの両側にポルノショップがある。Sex Shopと英語でも書いてある。そういう歓楽街の中心に「赤い風車」ことキャバレー・ムーランルージュがある。
ムーランルージュはロートレックのポスターや映画によって世界で最も有名なキャバレーになっている。ムーランルージュの前の道路に大型観光バスが止まり大勢の客が店内に入ってゆく。東京の「はとバス」の夜のコースのようなもので、観光コースの中にキャバレー・ムーランルージュが組み込まれている。
ムーランルージュのサイトを見ると、料金は相当高い。シャンペン付きの2時間ほどのショー見物で1万円以上、ディナー付きとなると5万円はする。
それだけの金を払って見るのは、今も昔も、ロートレックがポスターに描いたような踊り子のお尻である。
ムーランルージュは60人ほどのダンサーを雇用していて、その国籍は13か国にわたるが、最も多いのがイギリス人の23人で、フランス人は6人だ(英紙『デーリーメール』2019.1.4)。デーリーメール紙は「国籍は関係ない。大事なことはダンサーが自分たちの仕事の背景にある歴史と伝統を理解しているかどうかである」とムーランルージュの支配人の言葉を紹介している。国籍は関係ない、客が見たいのはお尻である、と言い換えもできよう。

夜が明けてから散歩がてらムーランルージュの前に行ってみた。歓楽のはての臭気と悲哀が漂っていると感じるのは、ムーランルージュに入るお金の持ち合わせがなかった貧乏旅行者の偏見だろうか。
8 モンマルトル墓地
パリで宿泊したモンマルトルのホテルの周辺をぶらぶら歩きしていたら、大きな墓地があった。墓地の上を高架になった道路がまたいでいる。そこから墓地を見下ろすとなかなか広い墓地だった。

あとで調べてみると、ドイツ生まれの作曲家・チェリストで、多くのオペレッタを作曲したオッフェンバックや『幻想交響曲』のベルリオーズ、いまさら説明の要もない作家・スタンダールや詩人・ハイネ、フランスのヌーベルバーグを代表する映画監督トリュフォー、画家のドガ、日本生まれの画家でこよなくパリを愛した荻須高徳の墓がある。
フランスのキリスト教徒の8割がたがカトリック教徒である。カトリックとイスラムは火葬をタブーとしてきたが、カトリックは1960年代に火葬を公認した。イスラム教徒はいぜん土葬にこだわっている。火葬が主流の日本では墓地のほとんどが火葬を前提にしたもので、土葬用の墓地は少ない。したがって、日本で死んだイスラム教徒を日本で土葬するには墓地探しが大変になる。
火葬後の骨壺を収める墓地なら現在都会で採用されているロッカー式の霊園で代用できるが、土葬となる難しいだろう。パリでも事情は似たようなもので、パリ市内に土葬ができる墓地を探すのは大変だし、見つかっても費用がかさむ。そういう事情で、パリはフランスで火葬の割合が最も高いところになっている。
Passant,
ne pleure pas sur ma mort:
Si
je vivais, tu serais mort.
通りがかりの人よ、私の死を悲しむなかれ
俺がもし生きていたらお前が死んでいる
これがフランス革命後の混乱の時代に恐怖政治を断行し、数多くの政敵を断頭台に送り、ついには自らも断頭台で首を斬られたロベスピエールの墓碑銘だと言われている。実は後日、誰かがロベスピエールに代わって書いたものらしい。ロベスピエールの墓はパリ市内の墓地にあったが、都市計画で墓地が廃止されたため、彼の遺骨は現在パリの地下納骨堂(カタコンブ・ド・パリ)に移されている。ここには何百万人もの遺骨か収められているので、ロベスピエールの骨を探すのは困難である。地下納骨堂はパリの観光スポットになっていて、年間数十万人が訪れる。納骨堂に下りたら「通りがかりの人よ…」という声がどこかから聞こえてくるかもしれない。
観光案内書でそんな話を読んでいたのだが、今回はカタコンブ・ド・パリへ行く時間がなかった。交通ストで地下鉄が止まっていたせいである。
モンマルトル墓地に入って気の利いた墓碑銘でも見たいものと、墓地の入り口を探したが、墓地の高い塀が延々と続き、入り口は見つからなかった。後で地図を見ると、入り口と逆の方向へ歩いていたようである。

9 モナ・リザ
 誰なんだろうね、モナ・リザの顔にヒゲをかき加えるいたずらをしたのは? 誰なんだろうね、モナ・リザの顔にヒゲをかき加えるいたずらをしたのは?
モナ・リザはミロのビーナスと並ぶルーブル美術館の至宝である。したがって、ルーブル館内にはモナ・リザの展示屋はこちら、と案内が表示されている。その案内板のモナ・リザにヒゲがあった。
ルーブル美術館はレオナルド・ダ・ビンチ(1452-1519)没後500年を記念して、2019年10月24日から2020年2月24日まで、巨匠の回顧展を開いた。ダ・ビンチの作品やダ・ビンチゆかりの芸術家の作品を世界中から集めて、彼の芸術の足どりを再検討しようという野心的な展覧会だ。
とはいえ、展覧会の構成は美術史家や美術館の学芸員向きの専門性が強すぎて、私のような門外漢には手に余るところがあった。生きている間にもう二度と見ることもないであろう作品がルーブルに集められ、ルーブルへ行ってそれをながめた、という高揚感はあったのだが……。
モナ・リザはダ・ビンチ回顧展の会場には移されず、いつも通り常設展の定位置に飾られていた。
パリの交通ストライキで館員の通勤がままならず、日によっては一部の展示室が閉じられることがあったのだが、ルーブルは見学者であふれていた。ピラミッドの周りには大勢の人が渦巻き、係員が予約の切符を持っている人はこちら、切符のない人はあちらへと人の波を仕分けしていた。
私は日本からインターネットで入場券を予約した。その予約は入場時刻まで指定する仕組みになっていた。

モナ・リザの部屋にたどり着くと、そこは超満員だった。モナ・リザが飾られている壁の前にロープで仕切られた鑑賞スペースが設けられ、その鑑賞スペースに入るために順番待ちの長い列ができていた。
モナ・リザの鑑賞スペースにたどり着いた人は、さっとモナ・リザを一瞥し、次にくるっとモナ・リザに背をむける。あれだけ苦労してたどり着いたモナ・リザの肖像だ。キャンバスに穴が開くほど凝視するのが普通だが……。

モナ・リザをバックにして記念撮影におさまるのである。モナ・リザは画集などで見てよく知っている。ルーブルに来た目的はモナ・リザと一緒に写真収まるためである。その気持ちはよくわかる。モナ・リザは凱旋門やオベリスク、エッフェル塔と同じパリの風景なのである。
 モンマルトルの宿泊ホテル近くのバス停からルーブル美術館まで直通で行けるバスに乗って午前10時にピラミッドの入り口に着いた。それから2時間ほど館内を回り、カフェテリアでサンドイッチのお昼を食べ、ダ・ビンチ回顧展を見て、再び常設展をめぐった。 モンマルトルの宿泊ホテル近くのバス停からルーブル美術館まで直通で行けるバスに乗って午前10時にピラミッドの入り口に着いた。それから2時間ほど館内を回り、カフェテリアでサンドイッチのお昼を食べ、ダ・ビンチ回顧展を見て、再び常設展をめぐった。
館内をさまよい歩くこと6時間。少々疲れて足どり重くたどりついたその部屋では子どもたちがお絵かきを楽しんでいた。絵画が展示されている部屋である。子ども向きの美術教育のワークショップらしいのだが、それを展示室でやるというのが大らかである。子どもが絵に落書きをするなどの心配はしていないのだろうか。
10 オルセーの世界の起源
セーヌ左岸のオルセー美術館はもともと鉄道の駅舎だった。
1889年のパリ万博に合わせてエッフェル塔が建設されたように、1900年のパリ万博の際はホテルを併設したオルセー駅が建設された。
しばらくは長距離列車のターミナル駅として活躍したが、第2次世界大戦までにはオルセー駅は使い勝手の悪い駅になってしまった。人々の移動距離が延び、長距離列車がより多くの車両を連結するようになり、全長が長くなった列車がオルセー駅におさまりきらなくなったからだ。
長距離列車のターミナルでなくなったオルセー駅の駅舎はホテルとして使われていたが、そのホテルが営業をやめると空きビル同然になった。その駅舎の構造を生かして1986年にオルセー美術館が生まれた。
したがって、オルセー美術館の壁面には、オルセー駅を偲ばせる巨大な時計が埋め込まれている。大時計のある美術館としてその名をはせている。

オルセー美術館には、19世紀後半を中心とした印象派の絵画の展示で有名である。そのオルセー美術館にギュスターブ・クールベの油彩『世界の起源』が展示されていた。公開展示されている世界中の絵画の中でもっともわいせつな絵として知られる作品である。
作者であるクールベも歴代の所有者も『世界の起源』を世間に知られないように隠し持った。この絵の最後の個人所有者である著名な哲学者ジャック・ラカンの死後、相続税としてラカンの遺族がフランス政府にこの絵を物納した。以来、オルセー美術館に展示されている。
芸術とわいせつをめぐる議論には果てしがない。オルセー美術館の『世界の起源』とルーブル美術館に展示されている銅像の一部をここに並べておき、結論はこの項をお読みの方の知性と感性にゆだねる。
 
さて、クールベが描いた『世界の起源』のモデルは誰だろうか、という推測があれこれと続けられてきたが、その謎が2018年に解き明かされた。
当時の報道によると、アレクサンドル・デュマの息子とジョルジュ・サンドの往復書簡を調べていた歴史学者が二人が交わした手紙の中から、オスマン・トルコの外交官の愛人・コンスタンス・クニョーだったことを偶然発見した。外交官が彼女をモデルに官能絵画を描いてくれとクールベに頼んだらしい。
AFP通信日本語サイト(AFPBB
2018.9.26)によると、発見者の歴史学者は、手紙を調べていて、「パリ・オペラ座バレエ団のミス・クニョーの最もデリケートで、最も堂々とした『インタビュー』を描写できる人はいない」と書かれた一節を不思議に思ったそうだ。そこで手書きの原本を調べて、インタビュー(interview、アンテルビュー)は「内部、秘部」を意味する「interieur(アンテリユール)」の間違いだったことに気付いたという。
なるほど、19世紀後半のオペラ座はこのシーリーズ第4回で書いたようにパリ在住の有閑階級の紳士にとって愛人の宝庫だった。
11
ファサード
達磨は壁とむきあうこと9年。モネはルーアン大聖堂のファサードとむきあって33の作品を残した。
モネの『ルーアン大聖堂』は世界中の美術館や個人が所蔵している。日本では箱根・仙石原のポーラ美術館が1点所有している。私は若いころボストン美術館でモネのルーアン大聖堂の絵を見たことがあった。大聖堂の形が光の中に溶けて崩れていくような絵だった。ニューヨークのメトロポリタン美術館やワシントンDCのナショナル・ギャッリー、モスクワのプーシキン美術館にもあるが、最大のコレクションはオルセー美術館に残されている。

2019年のクリスマスイブの午後、オルセー美術館には5点の『ルーアン大聖堂』が展示されていた。重苦しいゴシック様式のファサードを柔らかくつつむ光が描かれていた。
デジタルカメラでとらえた冬の薄曇りの午前のルーアン大聖堂はこんな感じだが(写真左)、PCで加工すると感じが違ってくる(同右)。
 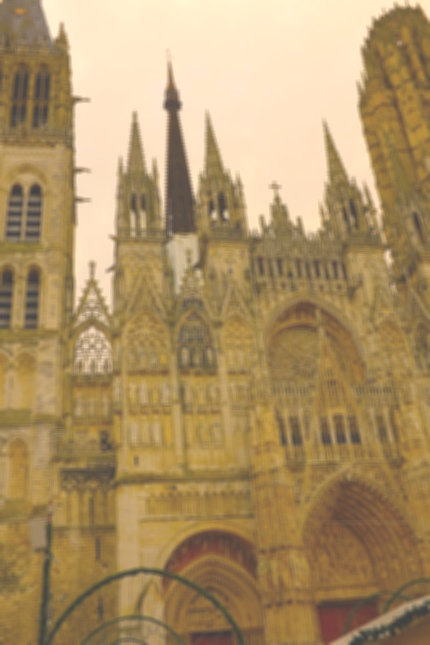
12 ノートルダム寺院
オルセー美術館で、ヨンキントが描いたセーヌ川の風景画を見た。ヨンキントはオランダ生まれの画家で、パリで活躍した印象派の先駆者。モネに大きな影響を与えた。

ヨンキントが19世紀半ばに制作したセーヌ川の風景画にノートルダム寺院がありし日のノートルダム寺院がかきこまれている。
パリ・シテ島のノートルダム寺院の尖塔が火事で焼け落ちたのは2019年4月のことだった。実物のノートルダム寺院は鋭意修復工事中である。2024年のパリオリンピックまでに修復工事を終えたとしているが、さて、間に合うかどうか。
焼け落ちたノートルダム寺院の周囲にはフェンスが張られ、やぐらを組んだその奥で、建物の修復工事が進められていた。

さすがに名高い名刹だけあって、火事直後から修復のための寄付の申し出が相次ぎ、昨年末の段階で1000億円以上の寄付の約束があった。フランス政府も寄付に対する減税措置を取った。
再建寄付金は国有財産保護財団、ノートルダム財団、フランス財団、国立博物館センターと税務署の5機関で受付けた。寄付金の受付先に国の機関が多く、税務署までが加わっているのが政教分離の点で奇異な感じを与える。
ノートルダム寺院の建物はフランスの国有財産であり、国有財産である寺院の建物をカソリック教団に無償で貸している。ノートルダム寺院は国有の文化財であり、その修復工事費捻出のために、フランス政府があれこれと税的優遇措置を取ることは問題ないとされている。日本でやっているふるさと納税と似たような考え方である。
何百億単位の寄付を申し出たのがルイ・ビトンやロレアルなどが何百億円もの寄付を申し出た。すると、労働組合などが、カネがあるなら労働者に還元すべきだと激しい批判を浴びせた。
(写真と文: 花崎泰雄)

|

