�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��6�́@�_���p�_�A�_���p�_ �U�U�@�X�n���g����ց\�\�O�t�� ���q�����́w�}���[����I�s�x���o�ł���Ă���܂��Ȃ���1942�N�A���{�͗���i�I�����_�̓��C���h�j�Ƃ��Ă����C���h�l�V�A���I�����_��������Ƃ����B1943�N�A�o�^���B�A�̓W���J���^�Ɖ������ꂽ�B3�N���܂�̓��{�R���Ɠ��{�̔s��́A���ʂƂ��āA�C���h�l�V�A�Ɨ��̏d�v�Ȍ_�@�ƂȂ�B�s�킪�߂Â�����A���{�̓C���h�l�V�A�ɑ��ď����̓Ɨ�����A���@���Ă̍쐬��F�߂��B1945�N8��15���A���{�̔s��ɂ���āA�ˑR�A�C���h�l�V�A�Ɍ��͂̐^�������B �C���h�l�V�A�ɂ͓Ɨ��푈�����߂̐������R���g�D�͂������A������Ȃ��A����Ƃ������Ɨ���̐����v���O�������Ȃ������B�Ⴂ�}�i�h�̂Ȃ������̂��ƂɁA�X�J���m�͓��{�s�킩��2�����8����17���A�ȃt�@�g�}���e�B���Ƃ�}���D�����������Ƃ�����g���̍����������Ɍf���ēƗ���錾����B�Ȍ�A�����I�ɂ킽���āA�C���h�l�V�A�̐l�X�͓��ꍑ�ƂƂ��ẴC���h�l�V�A�̐����c��ƁA�����x�z�����������������͂̈Ó��������炷�����I�����̂Ȃ����Ă������ƂɂȂ����B 1945�N����1949�N�ɂ����Ă͑I�����_�Ɨ��푈�ƃC���h�l�V�A�v���̎����B1950�N��͐��������`�̈ڐA�����Ƃ��̂����Ȃ����s���o������B50�N��̏I��肩��60�N��̂Ȃ�����ɂ����ẮA�C���h�l�V�A���Y�}�ƌR���̊낤���G�ΓI�����̏�ɂȂ肽�����w������閯���`�̂��ƂŁA�X�J���m�͏I�g�哝�̂𖼏�茠�Ў�`�I���X�H���̐�����W�J�����B�k���E�s���������E�n�m�C�E�W���J���^�����Ƃ���قǂ̍��J�[�u�H���������B����ŁA���ƍ�����o�ς͂قƂ�ǔj�Y��ԂɂȂ����B ���������X�J���m�̐��̕���������炵���̂�1965�N10��1�������̓�̑���9.30�����Ƃ���ɑ����R�̋��Y�}�r�ō��B���̋��Y�}���Ő��\���l�̎��҂��o���B������Ƃ����]���҂̐������܂��ɂ킩���Ă��Ȃ��B���Y�}���₻�̓����҂Ƃ݂Ȃ��ꂽ�l�X�͕����ʂ�̖��E���ꂽ�B  �X�J���m�ɂƂ��đ�����X�n���g�̂��ƂŁA���x�͈�]���āA�H���͐������ɂȂ����B��i���{��`�����̊��}�������āA�e�����E���z�̊C�O�����E�؊����e�R�ɂ����J������ƁA���̂��߂̗}���I���Ў�`�������ێ�����V�����i�I���f�E�o���[�j�̐��ւƁA�C���h�l�V�A�͘H����]�������B�X�n���g�̐��̂��ƂŁA�̐��ᔻ�͊J�����߂������߂̍��Ƃ̈���ƒ����𗐂����̂Ƃ��Č������e�����邱�ƂɂȂ����B���̐敺�ƂȂ����̂����R�ł���A�R�͍��h��荑�������ɌX�����B �Ɨ��錾�ȗ��A���܂��܂ȉ��l�ς�C�f�I���M�[���������O���[�v���C���h�l�V�A�̍��Ǝ哱���𑈂��Ă����B�C�X�����`����`�ҁA�C�X�������v�h�A�W�����`����`�ҁA�������Љ���`�A���邢�͋��Y��`��M����l�X�A�����āA�Ɨ��푈���炢���ƂƂ��ẴC���h�l�V�A�̔w���͌R�ł���A�R��������Љ���ɐϋɓI�ɎQ������͓̂��R�̌����ł���`���ł�����Ǝ咣�������Ă����C���h�l�V�A���R�ł���B �����̃O���[�v�͌܁Z�N��̖��吧����ɂ͂��������ƁA�A�i�[�L�[�Ȃ܂ł̔e������������Ђ낰�����A�X�J���m�̎w������̐����ŁA���R�ƃC���h�l�V�A���Y�}���̂����������͔͂r������ė͂��������B�X�n���g�̐��ɂȂ��Ă���́A���Y�}�͐�����f����A�c�]�̏����}���̐����ɕ������܂�Ė��Q�q���ȑ��݂ƂȂ����B�X�n���g�l�ƍ��R���ŏI���҂Ƃ��Đ����c�����̂ł���B �����܂ł��A�O�u���ɂ��āA�u�W�����Ǒz�v�̓X�n���g���߂��镨��ւƈڂ��Ă䂭�B �U�V�@���W���E�X�n���g 30�N�]�葱�����X�n���g�������˔@�A�����Ƃ����Ԃɕ����̂�1998�N6���̂��Ƃł������B���̂������O�ɒn���o�ł��ꂽ�X�n���g����������Θb�W�̒�����A�u�~�C�����X�n���g��m���Ă����v�Ƃ������b���Љ��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �āE�p�E�C���h�l�V�A��3�l�̍l�Êw�҂��G�W�v�g�̃s���~�b�h�����̖��H�Ŗ������B�ˑR�A����N���̂̃~�C�����N��������A3�l�̍l�Êw�҂ɋ߂Â��Ă����B�l�Êw�҂����͐^���ɂȂ����B�u�₠�A�l�Ԃǂ��A���O�������҂��H�@�ǂ����炫���̂��H�v�ƃ~�C�����s�C���Ȑ��Őq�˂��B�u���̖��̓}�C�P���B���卑�A�����J���痈�܂����B�~�C���l�v�B�A�����J�l�̍l�Êw�҂��������B�u�ӂށA�A�����J�H�@���̂悤�ȍ��͒m���ȁB�ŁA���܂��͂ǂ����痈���H�v�ƃ~�C���B�u�~�C���l�B���̖��̓`���[���Y�ŁA�C�M���X���痈�܂����v�Ƃ���1�l�̍l�Êw�҂��������B�u�C�M���X�H�@�m���Ȃ��B�ǂ��ɂ���̂��H�v�ƃ~�C�����d�˂Đq�˂��B�u���E�ő�̐A���n�鍑�ł����v�ƍl�Êw�ҁB�u�������A����ȍ��͒m���B�ōŌ�̂��O�A���܂��͂ǂ����痈���̂��H�v�ƃ~�C���B�u���̖��̓X�Q���Ɛ\���܂��āA�C���h�l�V�A����Q��܂����v�ƍŌ�̍l�Êw�҂��������B�u�ق��A�C���h�l�V�A�ƂȁI�@�����Ƃ��������v�ƃ~�C���̓C���h�l�V�A�l�̍l�Êw�҂ɖ����A�����q�˂��B�u����Łc�c�X�n���g�͂܂��W�����̉��l�iRaja Jawa�j������Ă���낤�ȁH�v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@ �X�n���g�̓C���h�l�V�A��30�N�]�茠�͂̍��ɋ����葱�����B�M�҂��W���J���^�Ńt�B�[���h���[�N���n�߂�����A�X�n���g�̑哝�̍ݐE�͂��ł�4�����I���Ă����B  �X�n���g�哝�̂䂩��̕i��W������W���J���^�x�O�̋L�O�ق� �C���h�l�V�A�Љ���ׂ����ώ@����ƁA�X�n���g�哝�̂̌�p���߂����āA���̂��낷�łɁA�X�n���g�ƌR�Ƃ̂������ɂ������Ⴍ�����ْ��W�������Ă����B�X�n���g�͌R���ȑO���͗�₩�ɂ������A�����̓����҂�o�p���邱�Ƃ������Ȃ����B�R�[�X�n���g�̊W���₦���ވ���ŁA�J������̐����������ԑw���C���h�l�V�A�Љ�̂Ȃ��ł��肶��Ɗg�債�Ă����B�܂��A���̏I���ɂ�鍑�ۊW�̕ω��Ȃǂɂ���āA�����[�����ƂɁA�C���h�l�V�A�ŃO���X�m�X�e�B�Ƃ������ׂ��A�J������u�N�g�D���u�J�A�� (keterbukaan)�v��1980�N�㖖����̗p����Ă����B �܂�A�X�n���g���R�������̐��������ێ����邽�߂ɂ́A�̐����G���[�g�̈ӌ�����łȂ��A�Љ�̗v���ɑ��Ă����������A���Ȃ��Ƃ��A���������|�[�Y���Ƃ�K�v�ɂ��܂���悤�ɂȂ����̂ł���B �X�n���g�����̊J������Ƃ����O��E���s���邩�����ŁA�؍��̖��剻�A�}���R�X������|�����t�B���s���́u���F���v���v�A��p�̖��剻����A�^�C�̖����ڍs���i�B�����������A�W�A�����̐����ω��́A�o�ϓI�ɖL���ɂȂ����l�X�����ɋ��߂���̂͐����̖��剻�ł���A�Ƃ��������̐����͂����߂Ă����B���킦�āA�āE�\�̗��\���͂��łɂȂ��A�����͂Ƃ����Ɋv���̗A�o��菤�i�̗A�o�ɊS���ڂ��Ă����B�������{��`�卑�́A�����ł���ǂ�ȗ}���I���Ƃł��ꉇ���E�삷��Ƃ����K�v���ɔ����Ȃ��Ȃ��Ă����B�o�ϓI���v�͕ʂɂ��Ă��A�X�n���g�̐��ێ��̐����I���v�͌������Ă����B �X�n���g���g�̘V��ƂƂ��ɁA�V�����̐����̂��̂ɂ��A�̐���J�̒������Ă��Ă����B���������������̕ω��ƁA�l�����I�ɂ킽���ăX�n���g���z�������Ă��������x�z�̐��̋��ł��A����2�̗v�f���͂���ɂ����Ȃ���A�C���h�l�V�A�E�E�H�b�`���[���������܂��܂ȗ\�������ĂĂ������ゾ�����B ���܂��܂ȗ\���͂��������A���������͂��������̂́A�߂������ɂ̓C���h�l�V�A�̖��剻�ڍs�͓���A�X�n���g�͎��ʂ܂ő哝�̐E�ɂƂǂ܂邾�낤�Ɨ\�����Ă����B�������A�����ɂ͌o�N�ɂ��̐���J�̒������ꕔ�ɂ����������B�����A�����̊�Ղ͂Ȃ���邬�Ȃ����̂Ɍ������B�X�n���g�͋c��A�s���{�A�R�A�Љ�c�́A�����ɂɂ�݂��������A���ʂ܂Ō��͂̍��ɂƂǂ܂�邾���̌��͂̍��i���Ȃ��ێ����Ă����B�܂��A���͂̍����~�肽���Ƃ̃X�n���g���g��ނ̈ꑰ�̂��Ƃ��l����ƁA���ǃX�n���g�͎��ʂ܂ő哝�̐E�ɂƂǂ܂炴������Ȃ��Ƃ���������������B�X�n���g�͓|��Ȃ����A���ނ����Ȃ��B1998�N3���̃X�n���g�哝�̂V�I�A�C�܂ŁA���������d�ꂵ�����͋C���Y���Ă����B �U�W�@�e�G�ŋ� ���łɂ��b�������Ǝv�����A�W���J���^�̒��S���ɂ���Ɨ��L�O�L�ꃁ�_���E�����f�J�ɂ��т���Ɨ��L�O�����i�X�̓W�]�䂩�猩���낷�ƁA���q�����̌������甼���I�ȏソ�������ł��A�W���J���^�̊X�ɂ͐Ԃ��O�̔g���c���Ă��邱�Ƃ��킩��B ���q�̓W���J���^�̉��������u�Ԃ��v�ƌ`�e�������A����͐ԂƂ������́A�W�����E�o�e�B�b�N�̊�ł��闕�ƒ��A���̒��F�̕����������߁A�����Ԃ��ۂ������悤�ȐF�ł���B���̐Ԃ����i���l�ɂȂ���Ď��������ł͐Ԃ����Ƃ����\�����g�����Ƃɂ���j�̊C�̒�ŕ�炵�Ă����l�X���A���肳�ꂽ���̂ł���Ƃ͂����A�ȑO�ɂ͂Ȃ������J��������o���������ƂŁA�����̃C���h�l�V�A�̍��Ƃ��Ă̂�������ǂ�Ȃӂ��ɍl���A�\�����n�߂��̂��낤���B�����m�肽���āA1990�N��̒�����M�҂̓W���J���^�ɂ���Ă����B ���������킯�ŁA�ȗ��A�M�҂́A���ẴI�����_�̓��C���h����ɂ̓I�����_�����̎������G�������h�̃l�b�N���X�Ƃ���ꂽ�킵���C���h�l�V�A�̎��R�A���i�A�����A�|�p�A�Ԓ������Ȃǂ͂������̂��ɂ��āA�����ς琭�����͂�����߂���l�Ԃ̐��L���b����Ɏ�������ނ��ƂɂȂ����B �܂��A�lj��ɂ₽�琭���ƃW���[�i���Y���̘b�肪�����Ȃ�͎̂���2�̗��R�ɂ��B�@����1�́A�M�҂�50�ŐV���Ћ߂���߁A1993�N����96�N�ɂ����āA�I�[�X�g�����A�E�����{�����̃��i�V����w�ŁA�V�ዾ�̂����b�ɂȂ�Ȃ���C���h�l�V�A�̐����ƃW���[�i���Y���ɂ��Ĕ��m�_���������Ă������Ƃɂ��B�w�ʘ_���ƂĊw�p�_���̂͂�����ł���A����Ȃ�ɏ������ɂ͂������邵���}�i�[�����߂�ꂽ�B���N�ɂ킽��V���L�҉ҋƂ̂����A���ۓI�ȗ������A�₪�Ă͗��j�̂��������Ɏ̂Ă�����悤�ȃG�s�\�[�h��S�V�b�v�̕��ɂ��ڂ������₩�����Ȃ����݂���ł��܂����g�ɂ́A�w�p�_���������Ƃ��ɑދ�����܂�Ȃ���ƂɎv���邱�Ƃ��������B����ȂƂ��A�茳�ɏW�߂����������ƂɋC�����ɏ����Ԃ��Ă������������̒lj��̂��ƂɂȂ����B ����1�̗��R�́A���̊w�ʘ_���̍ޗ��W�߂̂��߂ɁA�����ǂƂȂ��K��A�����1994�N�N����1995�N�ɂ����ďZ�݂����W���J���^�ɂ́A���́A���������̘b�������āA�����ȊO�ɊO���l�̋������Ђ��悤�Șb�肪����Ƃ����ĂȂ���������ł���B �����W�����ɂ̓{���u�h�D�[���̑��Ղ�A�v�����o�i���̂����₩�ȃq���h�D�[��ՃW���W�������O�����A�f�B�G�������̏����q���h�D�[�K���Ȃǂ����邪�A�����A���z�O�̃W���J���^�̍��������ق̒I�ɂ��낪���Ă�����̂́A�ق�������Ԃ����W�������l�̓��W���̕����ł������B  �����W�����̃W���N�W���J���^��\���Ől�X���_�����Ƃ���l�`�����̂����₩�Ȏ肳���ƌ��ɂ���ĉf���o�����e�G�ŋ��������Ɍ��Ƃ�A�����ق�Ė���ӂ����Ă��邱��A�W���J���^�̐l�����͗A�����̃R�J�R�[�������A���b�N�A�W���Y�A�n���E�b�h�f��Ŏ��Ԃ��Ԃ����A�Ђ��₩�Ȑ����k�c�Ŗ���߂��Ă����B��s�W���J���^�����̐��E�͉e�G�ŋ��������̂悤�ɕs�����ł��ڂ낾�B�w��œo��l���������_�����̋��O���ŁA�e�G�͋���ɂ��Ȃ�A�t�ɁA�⏬�������B�X�n���g�������̓����̃W���J���^�̐����k�c�̍s��������́A�����Ă��̂Ƃ���u�_�����͒N���v�Ƃ����Ƃ���Ɍ��������B  �W���J���^�̋N�����I�����_�x�z�ƌ��т���̂́A�C���h�l�V�A�l�ɂƂ��Ă͂��̖�����`�I���j�ς��炵�Ă��Ⴍ�̂��˂ŁA�ނ�̓I�����_�l������O����W���J���^�͑��݂����̂��Ǝ咣����̂����A�W���J���^�͂܂�����Ȃ��I�����_�̓��C���h�x�z�̒����Ƃ��Đ��܂����������s�s�ł���B �C���h�l�V�A���Ɨ����Ă܂��Ȃ�����u�W���J���^�̓C���h�l�V�A�Ƃ������̓��ɂ��炢�����������q���ł���v�B�����]�����̂̓X�}�g�����o�g�́A�C���h�l�V�A�ō��̍���w�ҁE���w�ҁE�N�w�҃^�N�f�B���E�A���V���o�i�������B���̐����̃q���������z���Ĕ삦����Α���قNj��͎��������������Ă����B �C���h�l�V�A�̌����z���q���̓����łʂ��ʂ��Ƃ��Ă���̂́A�����ƌo�ς̂�����ʂŃR�l�ɂ���đ��݂Ɍł�����Ă��鍂���ƃr�W�l�X�E���[�_�[�����������B����͂��܂ł��ɂ��������肾�B���͎ҁA���������A�R�l�A���ƉƁA�z���C�g�J���[�A�w�ҁA�|�p�ƁA�w���A�J���ҁA�n�����炱�܂��ȋ���������ړ��ĂɎ�s�ւȂ��ꂱ��ł���ז������\�\�C���h�l�V�A�̌��͂̒����W���J���^�ŁA�x�Ɨ͂̕��z���߂����Ă����̐l�тƂ����藐��A�삯����B ���Ў�`���Ƒ̐��̉��ŃW���[�i���Y�����`�����͂̎p�͗֊s�A���ߊ����s�N���ł���B�����₤�悤�ɂ��܂��܂Ȑ����S�V�b�v�₤�킳���������B�����āA����炷�ׂĂ��X�n���g�_�Ƃ���C���h�l�V�A���㐭���̓����Ƃǂ��ւ�肠���Ă���̂��\�\�V���L�҂�����̘V�����̃W���J���^�E�X�P�b�`�u�b�N�̑�ނƂ��Ă���ɂ܂���ʔ����l�^�͂��肦�Ȃ������B �U�X�@�X�n���g�̃_���p�_�� �X�n���g�̓W�����������̃W���N�W���J���^���ӂ̏����ȑ��Ő��܂ꂽ�B��������̃W�����l�ł���B�ނ̑�ꌾ��̓W������ŁA�C���h�l�V�A�̍���ł���C���h�l�V�A��́A�ނɂƂ��Ă͌�ɏK��������ꂾ�����B ���������āA�X�n���g�̃C���h�l�V�A��ɂ̓W�����Ȃ܂肪�������B�������a������������A����^�p��́A���@���a��i���j���������B�W�����l�̓C���h�l�V�A���\�����鏔�����̂����ōő�̃O���[�v�ł��邪�A�C���h�l�V�A�̍���Ƃ��Ă͓����̏������̋��ʌ��������}���[�ꂪ�C���h�l�V�A��Ɩ���ς��č̗p���ꂽ�B�������A�����ƌo�ς̒������W�����l����߂�ɂ��������āA�C���h�l�V�A��̃W���������i�s�����B���̏ے����哝�̃X�n���g�̃W�����a��C���h�l�V�A�ꂾ�����B  ����������ƁA�_���p�_�idaripada�j�Ƃ����O�u���̎g�����B�M�҂̓C���h�l�V�A��̐搶����A�_���p�_�Ƃ������t�́A�p��� �ethan�f�Ɠ����ŁA�������r����Ƃ��Ɏg���A�Ƌ�����ꂽ�B�C���h�l�V�A��̋��ȏ��ɂ����̂悤�ɏ����Ă������B�uA��B���傫���v�Ƃ����Ƃ� �edaripada B�f�Ƃ����������Ɏg���̂ł���B ���́u�_���p�_�v���X�n���g�͉p��� �eof�f�̂悤�Ɏg�����B���Ƃ��A���̃V���[�Y�̑�67��ŏЉ���X�n���g���h�̏Θb�́A�X�n���g��������4�����O�ɒn���o�ł��ꂽ�w�X�n���g���ɏ����ʁx�iMati Ketawa Cara Daripada Suharto�j�ɍڂ��Ă������̂��B���̏Θb�W�̃^�C�g�����̂��̂��X�n���g�ɑ��邠�Ă��ŁA�W���C���h�l�V�A��ł�Mati Ketawa Cara Suharto�ƂȂ��āAdaripada�͎g��Ȃ��B ���̃X�n���g�̃_���p�_�߂́A1990�N�㔼�̃C���h�l�V�A�ŕM�҂��X�n���g�̉����₨�b���e���r�Ō��Ă��Ă��Ȃ��݂ɂȂ����B�X�n���g�͑哝�̂Ƃ��ăC���h�l�V�A��̕��y�ɓw�߂����A���{�l�͐������C���h�l�V�A����g������Ȃ������B ����ǂ��납�A���͂Ƃ͋��낵�����̂ŁA�X�n���g���u�_���p�_�v��A������ɂ��������āA�X�n���g�̐����I��芪���i�������W�����l�����������j��A���������܂ł��X�n���g���a���^����悤�ɂȂ����B���̂���M�҂��������b�ł́A���̃_���p�_�߂̓X�n���g�������F�̃W���[�i���X�g����̊����ɂ܂Ŗ������Ă����B �C���h�l�V�A�l�̒��ɂ́A�W������͓��{��ȏ�ɕ��G�Ȍh��̎d�g�݂��������I�Ȍ���ł���A�����������ꂪ��Ă��W�����̐����������A�X�n���g�̎x�z���̃C���h�l�V�A�Ŏ嗬�����čs�����Ƃɔ�������l�����������B�{���͊Ȍ����ĂȂ͂��̃C���h�l�V�A��̃W���������A�����܂��ŁA�����ĉ�����A���ɈӖ��s���ĂȌ���ɂȂ��Ă���ƁA�ނ�͌����Ă����B �V�O�@�`����3.1���U�� ��C���ƍO�@��t��������ŃR�c���R�c���ƒn�ʂ����ƁA����s�v�c�A�������炱��Ɖ��N���o�����c�c�Ƃ����ӂ��ȁu�O�@��t�̉���`���v�͓��{�S���ɎU����Ă���B�O�@��t�͉���@��Ǝ҂̂͂��肩�Ǝv����قǁA���̐��͑����B ���̒��x�̓������̓`���Ȃ���Đ��ɗ����邪�A���Ɛ������͎҂̓`���ƂȂ�ƁA�����ɂ̓z�b�g�Ȑ����I���ʂ�����B����`���̂悤�ɊȒP�ɂ͂��܂����Ȃ��B���Ƃ��A�������̍R���Q�����E�R���w���҂Ƃ��ẲX�����Ɛт��A�ǂ��܂Ŏj���ŁA�ǂ����炪�`���Ȃ̂��B�\�A�����Ƀ��V�A���{�����J���������ȂǂŁA���������R�̓`����������������Ă���B���������R�̓`���ɂ́A�k���N�̎�̂ƂȂ��ĈȌ�́A�ނ̐����I���������������߂ɑn�삳�ꂽ�����������B �����悤�ɁA�������قǂł͂Ȃ����A�X�n���g�哝�̂��R�l����̐����Ȃ������`���������A����̎x�z�̐������̎x���A�Ȃ����͋��h�S�̈Ԃ߂Ƃ����B 1945�N�Ɏn�܂����C���h�l�V�A�Ɨ��푈�ŁA�C���h�l�V�A���a���̓I�����_�R�ɂ�����Ċ��F�������A�C���h�l�V�A���a�����{�͂₪�Ď�s�W���J���^���̂ĂāA�W���N�W���J���^�Ɉڂ炴������Ȃ��Ȃ����B����ɁA1948�N12���ɂ̓I�����_���̍U���ŁA�W���N�W���J���^���I�����_�R�ɐ�̂���A�哝�̂ł���X�J���m�̓I�����_�R�̕ߗ��ɂȂ��Ă��܂����B ���a�����͓Ɨ��푈�̐����w���҂��������B����ɂ�������炸�A�Ɨ��R�͌��݂ŁA�܂��Ɨ��푈�͑����Ă���̂��ƁA�C�O�Ɍ������ăf�����X�g���[�V���������邽�߂ɁA�Q�����������C���h�l�V�A�Ɨ��R��1949�N3��1���ɃW���N�W���J���^�ɑ��U�����������B���̍U���ŁA�Ɨ��R�͂킸��6���Ԃɂ����Ȃ��������A�W���N�W���J���^���I�����_����D�҂����B ���̉p�Y�I���U���Ă��A�������A�w�����Ƃ����̂������܂������������X�n���g�������Ƃ����`�����A�X�n���g�̑哝�̂Ƃ��Ă̌��͂̊g��ƂƂ��ɒ蒅���Ă������B�X�n���g���g���ނ̎��`�ł���������B�܂��A�X�n���g����̃C���h�l�V�A���j�ł���6���{�́w�C���h�l�V�A���j�x�ł��A�u3��1���̑��U���̓X�n���g�����i���哝�́j���w�������v�ƋL�q���ꂽ�B�܂��A���́w�C���h�l�V�A���j�x�͊ȗ��{�ɂȂ��č����w�Z�ł��g��ꂽ�B �������A�X�n���g�̎��オ�I��������܁A���ۂ̐퓬�Ŏw�����Ƃ����̂̓X�n���g�������������A���U������悵���̂̓W���N�W���J���^�̃X���^���������n�����N�u�E�H�m9���ł���Ƃ����A���j�̌��������i��ł���B�X�n���g����ɂ��ꕔ�̗��j�Ƃ�A�Ɨ��푈�ɎQ���������R�l�炪�A���U���̓X�n���g�̊��ł͂Ȃ��ƌ����Ă����B�X���^�����炪�C���h�l�V�A�l�̌R���j�Ƃɂ�����������Ƃ��������B 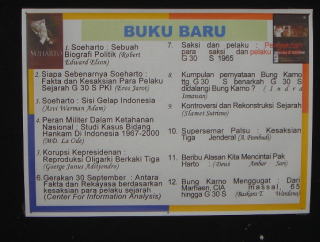 �X�n���g�����͂������Ă���A�X�n���g�̓`���̂߂������͂��n�߂��B����͂������낤�B�X�n���g�͂܂����Ԃ̋����c�ɂ̓Ɨ��R�̒����ɂ����Ȃ������B�W���N�W���J���^���U���̐����I�Ӗ��⍑�ێЉ�ɗ^����Ռ���\�����đ��U�������ł���قǐ����I�E�O��I�ɐ��n���Ă��Ȃ������B�X���^���̓s�ł���W���N�W���J���^�ɁA�X���^���̖��߂Ȃ��ő��U���������邾���̌��Ђ͓����̃X�n���g�ɂ͂Ȃ������B ���̂悤�Ȃ킩�肫�������������������Ă����Ă����Ȃ����Ă��܂��̂��A�������͂̂Ȃ�Ƃ��|���Ƃ���ł���B �V�P�@�X�}�C�����O�E�W�F�l���� �C���h�l�V�A�̏���哝�̃X�J���m����A�X�n���g�����͂������Ƃ��������̌��͓����ŁA��10���l�i100���l�ȏ�Ƃ�����������j�̃C���h�l�V�A�l���s�E���ꂽ�B20���I�̐��E�j�ł��w�܂�̐����I��ʋs�E�����ł���B�ŋߌ��\���ꂽ�O���ɂ��ƁA�č������̋s�E�ɉ��S���Ă����B���̘b�͉���Ȑ�����������ɖ����Ă���B���A���܂̂Ƃ���A����͂��Ă����c�c�B ���X�����e�����ւƂ������Ă������X�J���m�ɂƂ��Ă�����āA1960�N��̌㔼�A�X�n���g���v�������Ȃ��C���h�l�V�A�����̕\����ɖ��o�āA�e���ĘH���ւƑǂ����肩�����B�X�n���g�̑䓪�̓A�����J���͂��߂Ƃ��鉢�Ď��{��`�������犽�}���ꂽ�B ���̂���h�C�c���܂�̃W���[�i���X�gO. G. ���[�_�[���C���h�l�V�A�̐V�w���҃X�n���g�𐢊E�ɏЉ�悤�Ǝ��݂������̖���The Smiling General�ł���B���̒����̖`���Ń��[�_�[�́u�X�n���g���R�̓J�b�v�̂��������݁A�t��������点�Ȃ���A�I�n�������₳�Ȃ������v�ƃC���^�r���[�̂����̈�ۂ������Ă���B�{�̃^�C�g���͂�������Ƃ�ꂽ�B���̂���̃X�n���g�̎ʐ^�ɂ́A�͂ɂ��悤�Ȕ����ׂĂ�����̂����������B �̂��Ɏ���̌��͊�Ղ��ł܂�ƁA�X�n���g�͑哝�̂Ƃ��ċL�҉�ɗՂނ��Ƃ��A�����ׂ邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����B�哝�̊��@��W���J���^�̍����Z��n�E�����e���̃`�F���_�i�ʂ�ɂ���X�n���g���@�Ɏ艺�̊t�����Ăэ���ʼn������𖽂����B�X�n���g�������Ɋt�����Ƃ߂����ې����w�҂̃��E�H�m�E�X�_���\�m���X�n���g�ސw���1999�N�ɂȂ��āA�w�j���[���[�N�E�^�C���Y�x�̋L�҂ɘb�����Ƃ���ɂ��ƁA�X�n���g�͑哝�̎������̃f�X�N�ɍ���A�Ăэ��t���̊�𐳖ʂ��猩�������A�Ƃ����B�X�n���g�ƌ����������t���̂قƂ�ǂ��X�n���g�̋Î��Ɉؕ|�Ƃ����Ȃ�ʑ��݊����������B5�N��1��s��ꂽ�c��ł̑哝�̑I�o�ɂ������āA�����オ���āu������R���v�ƃX�n���g���I�Ɉًc��������E�C���������c���͂��Ȃ������A�ƃ��E�H�m�E�X�_���\�m�͌���������ł���B�X�n���g�̎����ƕ\��͂���قǂ̈ؕ|������������₩�ȗ͂�������������̂ɂȂ��Ă����B  �X�n���g�͎�����X���^���Ƃ��ăC���h�l�V�A���x�z�����B�X�n���g�ސw���O�̃A�W�A���Z��@�ɗh���Ԃ��Ă���C���h�l�V�A�ցA�����̕č��̃N�����g���哝�̂������f�[�������哝�̂���g�Ƃ��đ��������Ƃ��������B1998�N3���̂��Ƃ������B�����f�[���̓C���h�l�V�A����č��ɋA�邳���A�V���K�|�[���ɗ������A�����̃S�[�E�`���N�g���A���[�E�N�A�����[�㋉���Ɖ�k�����B���̐ȂŃ����f�[�����u�X�n���g�͈����҂Ȃ̂������Ȃ̂��H�v�ƃV���K�|�[���̎w���҂����̈ӌ������߂��B�O��I�z�������������������鎿�₾���A����ɑ��āA�X�n���g�̗ǂ��F���������[�E�N�A�����[�����̂悤�ɁA����܂������ȓ�����Ԃ����Ƃ����Ă���B �u�X�n���g�͑哝�̂����A�����̂��Ƃ�剤���̑�X���^�����Ǝv���Ă���B�X�n���g�͔ނ̑��q�►���\�������̉��q�≤���̂悤�ȓ���������ł���͓̂��R���Ǝv���Ă���B�X�n���g�͂܂��A�������g�������҂��Ƃ݂Ȃ��Ă���B�킽�����X�n���g���������Ƃ͍l���Ă��Ȃ��v ����L���ɂ���z�͖����`�҂łȂ��Ă��A�X���^���ł����Ă��A�����ł����Ă��A�����҂ł���D�ꂽ�א��ғz���A�Ƃ������[�E�N�A�����[�̐M���ɗ��t����ꂽ�X�n���g�]�ł���B �M�҂��W���J���^�؍ݒ��Ƀe���r�̃j���[�X�ŁA���łɎ�����C���h�l�V�A�̑�X���^���̒n�ʂɂ̂ڂ�߂��X�n���g���������i�����̃X�n���g�������̂͂�����1���j�A�Ί�����s�@�������ȁA�������\��̂Ƃ������������悤�ȋL��������B�I�n�����ׂĂ���X�n���g���e���r�Ō����̂́A���c����TVRI���������Ă����X�n���g�Ɣ_���̑Θb�̔ԑg�������B�����炭�ԑg�ɎQ������_���͐T�d�ɑI��A�_������X�n���g�ւ̎����ӌ��������ς݂������낤����A�X�n���g�ɂƂ��Ă͉q�����Q�̂�����肭�낰��PR�ԑg�������B ���̔ԑg�ŘV�X���^�����ƃX�n���g�������ׂ����ƁA�X�J���m���猠�͂�D�悵������̐��E�ł͂܂�����������40��㔼�̏��R�������ׂĂ������́A�͂����ē������̂��̂������̂��낤���B �V�Q�@�h�D�C�t���V �X�n���g��������̃C���h�l�V�A�ŁA�n���ŊJ���ꂽ��c��Z�~�i�[�Ȃǂ��̂����ɍs���ƁA��Î҂���n���̌R�l���Љ��邱�Ƃ��������B��c��Z�~�i�[�̎�Î҂��J�Òn�̗L�͎҂Ɍh�ӂ�\���ė��o�Ƃ��ď������������c�������n���̖��m�ɍ������āA�ǂ����Z�~�i�[�̃e�[�}�Ƃ͏�Ⴂ�ȌR�l���܂܂�Ă��邱�Ƃ����������B ���̂���R�ƌR�l�̓C���h�l�V�A�̃I�[�i�[�C���ł������B �����܂�Ō����A�C���h�l�V�A�̃I�����_�x�z�ɏI�~����ł��A�C���h�l�V�A�Ƃ������Ƃ̍\�����x���Ă����̂̓C���h�l�V�A���R�ł���Ƃ������������R�����Ɏp����A���������C�ɂ����M���Ă����i�{���̂Ƃ���́A�C���h�l�V�A�R�̓I�����_�̍U���ɔs��A�哝�̂ƕ��哝�̂܂ŃI�����_�̕ߗ��ɂȂ�̂������Ă��܂����B�C���h�l�V�A���Ɨ��ł����̂̓I�����_�Ɉ��͂������������̍��ې��_�̗͂��傫���j�B���������R�̌��т̐_�b���g���āA�u�R�̓�d�@�\�v�idwifungsi�A�h�D�C�t���V�Adual function�j�Ƃ������������ł����������B�C���h�l�V�A���ƌ`���̗��j�I�o�܂ɂ���āA���R�̓C���h�l�V�A�̈�̐��ƍ��Ƃ̈ێ��ɐӔC������A�R�͐����Ɋ֗^���邷�錠����L����Ƃ��������ł���B�R�����Ƃ͂����Ă����̂悤�ȗ��������˂����ČR���̐������͏����̍����ɂ�������B �X�n���g�������ŌR�l�������̐��E�i�o�����B���̍Ő�����1970�N�㖖�ŁA�����500�c�Ȓ�100�c�Ȃ��R�Ɋ��蓖�Ă�ꂽ�B����ɁA�������{�t���̖��A�B�m����3����2�A�ǒ����̍���������8���߂��A��g�̔������R�o�g�҂Ő�߂�ꂽ�B  ���������킯�ŁA�s�����������{�\�B���{�\�s���E���m���E�n���c��\�����\�S���\�����Ƃ����s���~�b�h�ɂȂ��Ă���̂ɑ��āA�C���h�l�V�A���R�́A���h�����ȁ\�R�Nj�\�R����\�R������\���R�x���Ƃ��������悤�ȃs���~�b�h�^�̍\���ɂȂ��Ă����B���ꂼ��̍s�����x���ɑΉ�����R�̑g�D���s���̂��ڕt�����Ƃ��Ēn���ɑ��݂��Ă����B������A��c��Z�~�i�[�̎�Î҂͓c�ɂ̑�\�����ɂ��������̂ł���B �C���h�l�V�A�R�͓Ɨ��푈�Ȍ�A�X�J���m����Ƀ}���[�V�A�Ƃ����肠���I�Ό�����ɂ��肾����A�X�n���g����ɂ͓��e�B���[���N�U�ɏo�������B�ΊO�I�Ȑ퓬�͂��ꂾ���ŁA���Ƃ͍����̔����{���͒����̂��߂̍�킪�傾�����B�R���̎�v�ȋ@�\�̈�́A���{�ɑR���鍑���̎Љ�͂�ł��ӂ����Ƃ����A�Ƃ��ɂ͌R���Ǝ��̔��f�Ő��{��|�����Ƃ�����B�b���ƂԂ��A�^�C�ł͈ꎞ���A���R�i�ߊ�����X�����������p���R���̎��オ�������B�R���̈��p����I���ł��̂����Șb�Ȃ̂ŁA�N�[�f�^�[�ŗ��R�w�ߊ��o�g�̎�Ǖ����A���̗��R�i�ߊ����ɏA�C���邱�Ƃ����������B�N�[�f�^�[�̓^�C�̖����ɂȂ������A���̍��ɔ�ׂė��������̋K�͂͏����������B �X�n���g��������A�R�͍I���ɐ����ɑR�������ȎЉ�͂���̂����ɓE�ݎ�����B���������āA�X�n���g�̐S�z�͌R�̗����ƃX�n���g�ɓ�������i���o�[2�̐��������������B�X�n���g�͌R��D�����A�i���o�[2�����͂��g�傷��ƌ����A�i���o�[3��i���o�[4���g���ăi���o�[2�̑����Ђ��ς����B���������30�]�N�C���h�l�V�A���x�z���������̂�����A�X�n���g�͂��̓��ł͂Ȃ��Ȃ��̍˔\���������j�������B �V�R�@ABS ���܂ǂ��̓��{�ŁuABS�v�Ƃ�����������������A�����Ă��̐l��anti-lock braking system�̂��Ƃ��Ǝv�����낤�B���̂���̃C���h�l�V�A�ł́AABS�Ɛq�˂���A�݂�Ȍ������낦�āu�A�T���E�o�p�E�X�i���v�iasal bapak senang�j�Ɠ��������Ƃ��낤�B�C���h�l�V�A��p�ꎫ�T�ł́A�gas long as the boss is happy�h�A�u�{�X�̌�S�̂܂܂Ɂv�Ɛ�������Ă���B �����ȃ^�J�����ɂ����Ȃ������牮�^���A���{�̖h�q�ȁi���j������������ɂ́u�牮�V�c�v�ȂǂƌĂ�Ă����̂��AABS�̂Ȃ���Ƃ������̂��낤�BABS�̓C���h�l�V�A�̓��Y�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���{���͂��ߐ��E���ɂ��錻�ۂȂ̂��B�����A�X�J���m�ƍَ��ォ��X�n���g����ɂ����ẴC���h�l�V�A�ł́A����ABS�nj�Q�������Ԃ錰���ł������B �X�n���g����̏Θb�B �\�\�X�n���g�͒ނ肪��������B���̂��Ƃ݂͂�Ȓm���Ă���B�ނ�ɏo������ƕK���啨��ނ肠���A���y�Y�Ɏ����A��B���̂��Ƃ��݂�Ȓm���Ă���B�����A���̂悤�ȉ\�͂��܂�m���Ă��Ȃ��B����́A�����������Ƃ��B�X�n���g���ނ�ɏo������O������A�i�ߊ��̖��߂ŊC�����̐����������ҋ@����B�X�n���g���ނ������C��ɁA�����A�����������啨�̋��������Đ���A�X�n���g�̒ސj�ɂ��̋����Ђ������Ă��B���̂��߂̑ҋ@�ł���B �X�n���g����芪���l�X�́A�e���̊��S�����ƃS�}����ɗ�B�X�n���g�e���ɋC�ɓ����Ă��炦�A���ƒn�ʂ�����邱�ƂɂȂ�B�������āA��芪���̓X�n���g�̊�F�����������A�X�n���g�̍l������肵�čs�������B�����Ă݂��ABS�ɂ�����ăX�n���g�t���͑哝�̂��ăW�����̉��l�ƂȂ����B����͕|���b�ł���B  �X�n���g�ɑ���ꂽ�v���[���g�̐��X�B�E��ɉH�q�������� �C���h�l�V�A�͓��{����̒���1945�N�ɏ����̓Ɨ��ɔ����Č��@���Ă�������B���̑��Ăɂ͍��Ƃɑ��鍑���E�l���E�s���E�����̌�����������Ə������܂�Ȃ������B�N���ψ���ł́A������������ނׂ����Ƃ����ӌ����o�����A�ψ������Ƃ߂��ێ�h�̖@�w�҂��A�C���h�l�V�A���Ƃ������̂��߂ɑ��݂���͎̂����ł���A���炽�߂č��Ƃɑ��鍑���̌����ȂǏ������ޕK�v���ǂ��ɂ���̂��ƈ�R�����B���̑��Ă��Ɨ���ɂ��̂܂܌��@�ƂȂ����B�X�n���g��Ɉꕔ�C������A���܂Ȃ������̃C���h�l�V�A���a�����@�Ƃ��đ��݂��Ă���B����܂��|���b�ł���B �A�����J���O�����@�������̂��̂͐l���̌����ւ̌��y�Ɍ����Ă����̂ŁA���X�ɂ����錠���͓T�Ƃ��錛�@�C��10������������ꂽ�B���̏C����2�����u�K�����閯���́A���R�ȍ��Ƃ̈��S�ɂƂ��ĕK�v�ł��邩��A�l���������ۗL���܂��g�т��錠���́A�����N���Ă͂Ȃ�Ȃ��v(A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.)�ŁA�e���ˎ����̂��тɘb��ɂȂ�B�l���ɕ��폊�L�̌�����F�߂�Ƃ������Ƃ́A�܂�Ƃ���A���{�ɑ��镐�͒�R�����l���̌����Ƃ��Č��@���F�߂Ă���Ƃ������Ƃł��낤�B ���{��Łu���i�����₯�j�v�Ƃ����ꍇ�A�L�����ɂ��Ƃ���́u���ƁE�Љ�܂��͐��ԁv�̂��ƂȂ̂��������B���������Ԃ�̂̂��ƂɂȂ邪�A�t4���̐V���̌o�ϖʂŁA�^�Ђ̖^�В����A�u��Ёv���Ђ�����Ԃ��u�Љ�v�ŁA�ǂ���Аl�͗ǂ��Љ�l�A�Ȃ�Ă��납�ȌP��������Ă���̂�ǂL��������B���{�ł͍��ƂƎЉ�ƌl�̑��݂̊Ԃ̊_���Ƃ������A�Η��ǖʂƂ������A���E���Ƃ������A�����������̂��Ȃ������܂��Ȃ܂܂ł���B �C���h�l�V�A�ł͓��{�ȏ�ɁA���Ƃɑ���Љ��l�̉e�����������B���������āA�X�n���g�ɑ���ABS�A�X�n���g�Ǝ�芪���̃p�g�����\�N���C�A���g�W���������ċ@�\���₷�������B���ɂ͍��Ƃ��C���h�l�V�A�̂�����̈��苒���A���̍��Ƃ̏�ɃX�n���g��������������Ƃ����}�����o���オ�����B �V�S�@�}�_���E�e�B���E�p�[�Z���g Kleptocracy �Ƃ������t������B�����ł́u���������v���邢�́u�D�_�������v�ȂǂƖ�Ă���B�Ƃ����Ɏ���ƂȂ�����������A�A�t���J�̂������̍��X�悤�ɂ��܂ł��|�s�����[�Ȍ����̌��t�̂Ƃ��������B���{����߂����ł́A���āA�}���R�X����̃t�B���s���A�X�n���g����̃C���h�l�V�A�������������B �}���R�X�����ɂ��炭���˂��s���~���͐���5,000���~�\2���~�Ɖ����b�Ɍ����Ă����B����A�Ď��w�t�H�[�u�X�x�ɂ��ƃX�n���g�̎��Y��160���ăh���i2���~��j�A�X�n���g�Ƃ��̃t�@�~���[�����Y��730���h���i8���~�j�Ƃ���ꂽ�B�w�^�C���x���X�n���g�s���~����150���h���ƕ��B�^�C�����̓X�n���g���疼�_�ʑ��ői����ꂽ���A�X�n���g�̑i���̓C���h�l�V�A�̈�A��R�őނ���ꂽ�B�������A���̏H�A�������X�n���g�i��h�Ōł߂��C���h�l�V�A�ō��ق́w�^�C���x�ɋt�]�s�i�̔��f���������B�ō��ق́w�^�C���x��1���h���̔����𖽂����B����ɂ́w�^�C���x�����ł͂Ȃ��A�C���h�l�V�A�l�̑������т�����V�����B���m�ȋ��z�͂Ƃ�����A�X�n���g�Ƃ��̈ꑰ���Ƃ�ł��Ȃ��z�̕s���~�������Ă������Ƃ̓C���h�l�V�A�l�̏펯���������炾�B �X�n���g���㖖���̃C���h�l�V�A�ł����₩�ꂽ���h���b�B�t�F���f�B�i���h�E�}���R�X�ƃX�n���g�̍ȃe�B���E�X�n���g�͂��łɋS�Ђɓ����Ă����B�C�����_�E�}���R�X�ƃX�n���g�͐����Ă����B �\�\�₪�ăX�n���g���C�����_�E�}���R�X�����ɁA�ނ�͂��̐��ōĉ���B�V������Ȃ��B�������A�n���ł��B��������A�n���B�C�����_�ƃt�F���f�B�i���h�̃}���R�X�v�Ȃ͌���������܂ʼn����ɂ����Ă����Ղ����Ղ��Ă����B�u�悤�A�t�F���f�B�i���h�I�v�Ƃ����ăX�n���g�����ꂽ�B����Ɖ����̓X�n���g�̃w�\������܂ł����Ȃ��B����ɍȂ̃e�B���̎p����������Ȃ��B�u�H�v�ƃ}���R�X�v�w���q�˂��B�X�n���g�͏݂��ׂĎ����̑�����������w�������B�t�F���f�B�i���h�������Ă݂�ƁA���A�n���̒�Ńe�B���E�X�n���g�������ɂȂ�A���̔w���ݑ�ɂ��ăX�n���g�������Ă����B  �e�B���E�X�n���g ���̘b���C���h�l�V�A�l�ɂ��������������R�́A�X�n���g�ȏ�Ƀe�B���v�l�������Ă������炾�B�哝�̂��v�w�œ����悤�ɍ��Ƃ̕x�������˂Ă��A���̏ꍇ�͒j�̏ꍇ������������Ƃ����W�F���_�[�E�o�C�A�X���w�i�ɂ���B����͂�����������A�}�_���E�e�B���������āg�o�N�V�[�V�h���������ȕ��ł͂Ȃ������B �e�B����Tien�ƒԂ�BTien�̓C���h�l�V�A��A���n�ɂ��Ă����I�����_�̌��t�Łu10�v�B�p��́u�e���v�̂��Ƃł���B�ޏ��͊C�O�̃��f�B�A���� �u�}�_���E�e�B���i�e���j�E�p�[�Z���g�v�Ƃ�������t�����Ă����B�哝�̂ł���v�̗���𗘗p���āA�C�O���玝�����܂�鏤�k�Ɋ��荞��ł́A�R�~�b�V������v�����Ă����̂ŁA�u�}�_��10�p�[�Z���g�v�Ƃ����j�b�N�l�[�������炤���ƂɂȂ����Ƃ����Ă����B�牮�v�l�̂悤�Ȃ��܂��܂����^�J���Ƃ͌��Ⴂ�̋��z�ł������Ƃ����Ă���B �X�n���g�̑��q�►�����e�̒n�ʂ𗘗p���Ă��ꂼ��̃r�W�l�X�E�`�����X���g�債���B�������������������v���I�ȍ����̑����Ɏ���Ȃ��悤�ɁA��e�ł���}�_���E�e�B�����Ƒ����̗������������Ƃ߂Ă����B�X�n���g�͕\�Ō��͂�ێ����A���̌��͂��e�R�Ƀt�@�~���[�E�r�W�l�X���d���Ă����������}�_���E�e�B���������̂ł���B �V�T�@��l�O�r �X�n���g�̍ȁA���̃e�B�����ƃV�e�B�E�n���e�B�i�E�X�n���g�́A�����܂�������NHK��̓h���}�Ȃǂł��Ȃ��݂́u�R����L�̍ȁv�̂悤�ɁA�X�n���g�ɂƂ��ĕs���ȑ��݂������B ����܂��A�X�n���g���㖖���ɂ͂�������b�\�\�B �V���K�|�[���̃��[�E�N�A�����[�͎�ނ����̂��A�㋉��b�ɂȂ��ĉ@�����������B�d���͌����̎���قǖZ�����Ȃ��Ȃ����̂ŁA�ɂȂƂ��͏���������ē����p�̃R���T���^���g�̂悤�Ȃ��Ƃ��n�߂��B����ӂ̂��ƁB�^���֏o�����Ă������[�E�N�A�����[����X�n���g�̎���ɓd�b���������Ă����B�u���͂����������������̂��Ƃ�q�˂��Ă���B�ǂ����@���v�����Ȃ��B�m�b��݂��Ă���Ȃ����v�Ƃ����˗��������B�X�n���g���d�b���ł����������B�u�����Ƃ��B�����A�d�b���Ȃ��ł��̂܂܂�����Ƃ����҂��Ă��Ă���Ȃ����B�����e�B���ɕ����Ă���v  ������͂��Ȃ�M�p�ł����ژ^�ŏЉ�ꂽ�G�s�\�[�h�\�\�B �X�J���m���琭����D�悵���X�n���g�́A�������M�����A�l�C�������W���N�W���J���^�̃X���^���E�n�����N�u�E�H�m9���哝�̂ɑI�B�������A1970�N��ɓ���ƃn�����N�u�E�H�m9���̓X�n���g�̐�����@�Ɍ��C�������Đ���������A�W���N�W���J���^�ɋA���Ă������B���̃n�����N�u�E�H�m9�����畷�����b���A�X�n���g�ɂ���ē������ꂽ���Ƃ����钆���n�̃C���h�l�V�A�l�A�E�B��`���[�^�b�c����ژ^�ɏ����c�����B�E�B�E�`���[�^�b�c�̓X�J���m���������̊t����1966�N��3��11�����ߏ�����ɓ��ꂽ�X�n���g�ɂ���ė�3��12���ɑߕ߂���C1977�N�܂œ�������Ă����B�E�B�E�`���[�^�b�c�����A���̗L����ƃv�����f�B�A�E�A�i���^�E�g�D�[�������M�������̉�ژ^�Ƀe�B���E�X�n���g�̓����̌����`����Ă���B����[�H��̂Ƃ��A�n�����N�u�E�H9�������g�̎��C�ƌ�p�҂Ɋւ��鏔����b���������߂ɃX�n���g�哝�̂ɌĂꂽ�Ƃ��̂��Ƃ��E�B�E�`���[�^�b�c�Ɍ�����B���̃X�n���g�E�X���^����k�̐Ȃɂ̓X�n���g�������̐肢�t�_�������ׂ͂��Ă��āC�b�������ɉ�������B�X�n���g�Ɍ��C�������Ă����n�����N�u�E�H�m9���́A�l�ƈꏏ�ɌN����߂���ǂ����A�ƃX�n���g�ɔ������B�ƁC�ˑR�C�哝�̕v�l�����̏�Ɍ���C�b�������Ɋ����ē������B�u�������A�p�N�E�n���g�͐����Ă��邩����哝�̂ł��B���C�Ȃǖ��O�ł��v�B�e�B���E�X�n���g�͂������Ƃ����B 1994�N���납��X�n���g�ɂƂ��Ă��������̂Ȃ��p�[�g�i�[�A�e�B���E�X�n���g�̗̑͂̐����������̖ڂɍL���ӂ��悤�ɂȂ����B���Ƃ��A1994�N10��1����9.30�����̒Ǔ����T�̂����A�����̏����ɕ�������悤�ɂ��āA����̃p���`���V���E�T�N�e�B�Ɍ���ꂽ�e�B���͋r�̐����̂��߂ɂ�����A���₤���|�ꂻ���ɂȂ����B���̃V�[���̓e���r�Ő����p���ꂽ�B�܂��A1995�N2��11���A�}�i�h�ŊJ���ꂽ�V���̓��̋L�O���T�ł́A�����悤�ɋr������Ă��߂��A���ɂ����Q���҂��牟���E�����悤�ȋ����̐�������A��u�A��ꂪ�ٔ����ɂ܂ꂽ�B���̂Ƃ��͕M�҂��J��ɂ��Ėڌ������B 1996�N4��28���A�V�e�B�E�n���e�B�i�E�X�n���g���S����Ⴢ̂��߃W���J���^�s���̕a�@�Ŏ��������B72�������B�n�R�l�̎q�ǂ��X�n���g�ƋM���Ƃ͂�������̃e�B�����A2�l���Ēz�������Ă��������ɂ��̂т�邽�������\�����鎀�ł������B �V�U�@�`�F���_�i�̂��B�� �X�n���g��1921�N6��8�����܂ꂾ����A2008�N�ƂȂ������N�A87�̒a�������}���邱�ƂɂȂ�BWHO��2007�N�̓��v�ɂ��ƁA�C���h�l�V�A�l�j���̕��ώ�����66������A�X�n���g�͒����Ɍb�܂�Ă���B �X�n���g�̑O�C�҂���������哝�̃X�J���m�́A�X�n���g�̂���Č��͂̍�����ǂ����Ƃ���A�����։��ŔӔN���������A1970�N6���A���O�̂����Ɏ����}�����B69�������B������v���ƁA10�N�O��1998�N5��21���A �gHang Suharto�h �gGantung Suharto�h �u�X�n���g��݂邹�v�Ƃ����f�����̓{���̒��ŁA����������������ׂđ哝�̂̈֎q���狎�����l���ɂ͕s�������ȉ��₩�ȔӔN�𑗂��Ă���B �X�n���g�͌��E�哝�̂̎��ォ��W���J���^���S���̃����e���n��ɂ���`�F���_�i�ʂ�Ɏ��@���\���Ă����B�ނ����E�̎���ɂ́u�`�F���_�i�i���h�j�v�Ƃ����A�哝�̂Ƃ��̉Ƒ��̂��Ƃł������B�Â�����̘b�ɂȂ邪�A�u�Z�g���v�Ƃ����Ε������Ƃ��̈ꑰ���Ӗ������̂Ɠ����ł���B �X�n���g�͑哝�̐E��ǂ��Ĉȗ��A���̎��@�ɕ�������������ł���B�O�o�͒����o���œ��@����Ȃǂ̕a�@�ʂ����x���B�މ@����Ƃ��̃X�n���g�̎ʐ^��V���Ō������Ƃ�����B�Ԉ֎q�ɍ���A���̕\��͍ŔӔN�̖ёA�������A���i���h�E���[�K���炪�����ł������悤�ɁA�ڂɗ͂��Ȃ��A�\��̂���A���C�̂Ȃ������̕������N��肾�����B �C���h�l�V�A�̌o�ϊJ���Ɍ��͂��������A����ʼn~�ɂ��Ē��P�ʂ̋������ɂ��炭���ˁA����ɂ̓X�J���m����̌��͒D��ɂ������ăC���h�l�V�A���Y�}���Ƃ��̎x���ҁA���̊W���Ȃ��_�����10���l����100���l�̒P�ʂŋs�E���������̑��ӔC�҂Ƃ��ẮA�K�^�Ȃقlj��₩�ȗ]���𑗂��Ă���B �J���{�W�A�̋s�E�̐ӔC�҂͂Ƃ��Ƃ��ٔ��ɂ�����ꂽ���A�X�n���g�̏ꍇ�͂��������������Ȃ��B���̑�ʋs�E�̉��Q�҂ł���R�l�A�C�X�������k�A��Q�҂̉Ƒ��炪�Ȃ��������ŁA�ٔ����i�W����A�������^����ɂȂ鎖�ԂɎ���\��������B���̂����A�č����{���s�E�ɉ��S���Ă���B�C���h�l�V�A���Y�}���̖�����C���h�l�V�A�R�ɓn���Ă����B ����A�X�n���g�̕s���~���́A��������͋N�i���ꂽ���̂́A�퍐�ł���X�n���g���a�C�̂��ߌ����ɂ������Ȃ��Ƃ������R�ŁA�ٔ��͒��~����Ă��܂����B���݂̃C���h�l�V�A�̎w���҂����̓X�n���g����ɗ��g�o���̊K�i���̂ڂ������̂������B�X�n���g�̕s���~�����O��I�ɖ\���������A�Ƃ�������������˂Ȃ��L�͎҂������B���݂̗L�͎҂̑����̓X�n���g�ɑ����̉��`������A����Ȃ�ɑ��h�������Ă���B�X�n���g��30�N�]��������ăC���h�l�V�A�Ƃ������������܂ŕ��コ�����w���҂ł�����B�Ȃɂ͂Ƃ�����A���̌��тƂЂ������ɉߋ��̉��_�͐��ɗ����Ă�����ق����A�₽��g���𗧂Ă�����܂����A���ꂪ��l�̒m�b���Ă��A�Ȃǂƍl���Ă���̂��낤�B  ���̐������A�Ƃ����Ă��C���h�l�V�A�ł͓��{�̂悤�Ȃɂ��ɂ������V�N�̂��j���͂��Ȃ����A�X�n���g�V�̓`�F���_�i�̓@��ɂ������āA�v�������Ȃ����i���]���ɕt��������ꂽ�V�����N�̏��߂��̂�т�߂��Ă��邱�Ƃ��낤�B ���N�̏H�A�w�j���[���[�N�E�^�C���Y�x���X�n���g�̉B�������Ԃ���L���ɂ����B���̋L���̒��ŁA�X�n���g�ɍD�ӓI�ȕ]�` Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President ���o�ł���Retnowati Abdulgani-Knapp �̃R�����g�����p����Ă����B���g�m���e�B�̓��X�����E�A�u�h�D���K�j�̖��ł���B�X�J���m���ォ��X�n���g���コ��ɂ̓��K���e�B�E�X�J���m�v�g�D���̎���܂ŁA�I�݂ȗV�j�p�Ō��͂���r������邱�ƂȂ��������������I�҂ł���B�����������e�ƃX�n���g�̉��ŁA���g�m���e�B�̓X�n���g�@�̏o���肪�F�߂��āA�]�`���������̂��낤�B ���̃��g�m���e�B���j���[���[�N�E�^�C���Y���̋L�҂Ɍ�����Ƃ���ł́A�X�n���g��10�N�Ԏ��@�ɕ��������Ă���̂́A����Ύ����I�����ւŁA�������邱�Ƃɂ���ĉߋ��̔�������A�����ֈڂ鏀�������Ă���悤�ɂ݂�������̂��������B ��N���K���������c�N�v�͗��̏I���ɍE�q�_��K�ꂽ�B�E�q�͐����Ɠ��������ʏ�Ō�����B���A�W�A���ł͂��܂��ɂ��̋����̉e�����c���Ă���B���邢�͎c���Ă���悤�ɑ����Ă���B�����A�X�n���g�̉��₩�ȉB���������݂邩����A�����I�s�ׂƐ����̏C����Ƃ͂Ȃ�̊W���Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��悭�킩��B����ȕx�A�傫�Ȗ��_���l�����邱�Ƃ͗͂̂��邵�ł���A���̏ꍇ�A�s�ׂ̐��A�s���Ȃǖ��_�Ƃ͂Ȃ�̂��������Ȃ��\�\���_�Ƃ͂����͂ɑ���]���݂̂ɂ������Ă��邩�炾�A�ƃz�b�u�X�͌����Ă���B�X�n���g�V�͂��̂悤�Ȗ��_�̖��c�ŗ]��������ɑ����Ă���B�ނ́w�����@�C�A�T���x��ǂ�ł����̂��낤���B �V�V�@�����T�� 1��5���̃C���h�l�V�A�̐V���i�E�F�u�Łj�ɂ��ƁA�X�n���g�͌��N��Ԃ�������������4���A�v���^�~�i�a�@�ɋً}���@�����B�X�V���E�o���o���E���h���m�哝�̂���5���A�������̂��ߓ��a�@��K�ꂽ���ƁA��t�c�ɂ��Əd�Ăȏ�Ԃ��Ƃ̂��Ƃ��A�ƋL�Ғc�Ɍ�����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Ď��w�^�C���x���X�n���g�̕s���~����2007�N�H�A�C���h�l�V�A�̍ō��قŔs�i�A100���~���鑹�Q�������x�������������b�͂��łɂ����B�Ƃ�ł��Ȃ������ł���ƁA���X�x��āA���̔N�̕���29���̎А��Łw�j���[���[�N�E�^�C���Y�x���ᔻ�����B ���E�̓r�㍑�̍��ɂ���N��100���~�̌����������˂��Ă���A�Ɛ��E��s�͐��肵�Ă���B�X�n���g�͂��������r�㍑�̍������牡�̔ƂƖ��w������Ă��郏�[�X�g10�̎w���҂̈�l�������Ɛ��E��s�݂͂Ȃ��Ă���B ���E��s�͂܂��ANGO�E�g�����X�y�A�����V�[�E�C���^�[�i�V���i���̐��������p���āA�X�n���g�̎��Y��150���h������350���h���Ƃ݂Ȃ����B �����W���J���^�Ńt�B�[���h���[�N�����Ă���1990�N��O���A�V���Ȃǂł݂��X�n���g�哝�̂̔N���300���~�ɂ������Ȃ������B�哝�̂Ƃ��Ă̐��K�̎����ɂ����ł͂��ꂾ���̎��Y�͒z���Ȃ��B�X�n���g�͏�X�A������F����א����Ă���悤�Ȏ��Y�͎����Ă��Ȃ��ƌ����Ă����B�������A�����^�Ɏ�l�͂ǂ���T���Ă�����͂��͂Ȃ���������ǁc�c�B �哝�̂̈Ќ��������Đg���ŋ��ڂ̎��Ƃ�Ɛ肵����A�R�~�b�V���������Ȃǂ̂��肫����̘B���p�̂ق��A�X�n���g�Ɠ��̏W���p���C���h�l�V�A��Ń����T���iyayasan�j�Ƃ�����c�̐ݗ��������B���c�͕\�����Љ����ړI�ɐݗ�����邪�A�X�n���g�͂�����W���@�\�Ƃ��ė��p�����B �X�n���g�͂��������W�����c�̗������E��10�ȏ�����߂Ă����B1970�N��̌㔼����A�@�߂ɂ���č��c��Ƃ̎��v��5�p�[�Z���g�������������c�Ɋ�t�������B�₪�č��c��Ƃ����ł͂������炸�A���Ԋ�Ƃ⍂�z�����҂������t���`���t�����B ��t�s�ׂ̓C�X�����̌܍s�i�M�����A��q�A��́A�f�H�A����j�̈�ł����́i�U�J�[�g�j �ł���B�W���̖��ڂ̓t�B�����\���s�[�������������A���ۂ̂Ƃ���́A��t���̑����͍��c�����œK���ɏ�������A�X�n���g�ꑰ�������Ɏg�����Ƃ����Ă���B  �X�n���g�͒����W�����̃f�B�|�l�S���t�c�������Ă������납��A���c�������ċ����W�߁A�z���̕��m�̗����^�ȂǂɉĂ����B�܂��A�̂��ɃX�n���g�̃N���[�j�[�ƂȂ鏤�l�����Ɛe����[�߂��B���c�ƃN���[�j�[���g���Ė��A�Ȃǂ��肪���Ă����Ƃ����B�X�n���g�͋��K���o�ɒ������R�l�������B �M�҂��W���J���^�Ńt�B�[���h���[�N�����Ă������됢�b�ɂȂ����A�g�}�N�X�}�̓W���[�i���X�g���C�������o�K�E�y���X�E�h�N�g���E�X�g���̏����������B���̌��C���̓��f�B�A�Ȃǂ���̊���ʼn^�c����Ă����B�t�@���h���C�W���O�������̎d���������B ����Ƃ��A�A�g�}�N�X�}�����C���̉^�c�ɂ����Ƃ������̂���^��胁�f�B�A�̌o�c�҂Ɖ^�c�����̂��ƂŘb�������Ă����Ƃ��A���̌o�c�҂�����Ȃ��Ƃ��������B �ނ��o�c���郁�f�B�A��Ƒ̂�A�ތl�̎�������X�n���g�̍��c�Ɋ�t�������Ă���������C���ɉȂ����낤���ƍl���āA�o�҂͏���b�̂��Ƃ�K�ꂽ�B����b�̓n�����R�Ƃ������̐l���ŁA�X�n���g�̑��߈�l�������B�X�n���g�̍��c�ɔ[�߂�����A�W���[�i���X�g���C���Ɋ�t�ł���悤�X�n���g�ɗ���ł���Ȃ����A�Ƃ��̌o�c�҂͏���b�Ɍ������B����ƁA����b�͕\�������点�A����Ȃ��ƃo�p�iBapak�j�Ɍ�����킯���Ȃ����낤�A�Ɣߖ̂悤�ȋ��ѐ����������Ƃ����B �V�W�@�X�n���g�_�\�A�X�^�i�E�M���E�o�O�� 2008�N�̐���4���A86�̃X�n���g�V���̒�������ăW���J���^�E�N�o�������n��ɂ���v���^�~�i�����a�@�ɓ��@�����B�C���h�l�V�A�̐Ζ��E�K�X���Ѓv���^�~�i�n��̗��h�ȕa�@�ł���B�X�n���g�͌��C�����ς��̑s�N�̂��납��v���^�~�i�ɂ͐��b�ɂȂ��Ă����B�����̃v���^�~�i�̓C���h�l�V�A���R�̋��ɂ̂悤�ȍ��L�Ζ���ЂŁA�R�o�g�̏��㑍�ق̃C�u�k�E�X�g�E�H�̓X�n���g�����̋��ɔԂł�����A�ނ�ʂ��đ�����X�n���g�ɗ��ꂽ�Ƃ���Ă���B �X�n���g���v���^�~�i�����a�@�ɓ��@�����̂͐S���Ɛt���̋@�\�̒ቺ�����R�������B�Ђǂ��n���Ƃނ��݁B���@�̗�����5���ɂ̓X�V���E�o���o���E���h���m�哝�̂��X�n���g�����������B���̂��ƂŃ��h���m���L�Ғc�ɁA�d�Ăȏ�Ԃ��ƈ�t�c���畷�����ꂽ�A�ƌ�������Ƃ���A�������傫���Ȃ����B ���t���͂�A�����s���A�̓��ɂ��܂��Ă��������ʂ����Ƃ���A�X�n���g��6���[�܂łɂ͏Ǐ����⎝���������B6���̓��j���̒��ɂ̓��h���m���t�̊t����1�l���������ɖK�ꂽ�B�ނ��X�n���g�̕a�������낤�Ƃ����Ƃ���ŁA�X�n���g���ڂ��J���u���܉������납�ȁH�v�Ƃ����˂��Ƃ����B�u���߂ł��v�Ɠ�����ƁA�X�n���g�̓C�X�������̐��߂̋F��̌��t���x�b�h�̒��łԂ₢���������B �X�n���g�̕a��͏������P���ꂽ�悤�Ɍ�������̂́A�������s����ŁA�ˑR�Ƃ��Č��������A�ƈ�t�c�͐������Ă���B ���@�����X�n���g�����E�哝�̂̃��h���m��t�����������������B�X�n���g�̎q�ǂ�������g���̂ق��A�X�n���g��������̊t��������X�Ƃ���ė����B �ւ�Ȍ����������A�C���h�l�V�A�̃��f�B�A�̕��������{�œǂ�ł���ƁA������Ƃ����u�X�n���g�E�f�[�v�̂悤�ȓ��X�������B�Ȃ��ɂ̓X�n���g��������̗^�}�S���J���̗�������ރS���J���}�̃A�O���E���N�\�m����c���̂悤�ɁA�l���I�ȗ��R����X�n���g�̉��E�ٔ������S�ɂ�߂Ă͂ǂ����i���Ȃ݂�2006�N�̃X�n���g�̏d�a�E���@�����������ɁA�a��𗝗R�ɃX�n���g�ɑ���ٔ��͌Y����������s���~���̕Ԋ҂����߂閯���i�ׂɐ肩�����Ă���j�A�Ƃ��������܂ŏo��悤�ɂȂ����i1��5���j�B1��6���̖������W�I�ł́A����C�X�������j�w�҂��A�u�X�n���g�͌o�ςƊJ���ōv�������B�C���h�l�V�A�����͂��̂�����Ŕނ������Ă��E�C�����Ƃ��v�ƌĂт������B6���̃A���^���ʐM�ɂ��ƁA��4��̑哝�̂������A�u�h�D�����t�}���E���q�h���X�n���g���������A�X�n���g�����͂̍��ɂ������Ƃ��ɊԈႢ��Ƃ������Ƃ͊m���ł��邪�A����ŁA���Ƃƍ����ɍv�������������Ƃ��܂������ł���A�������a�߂�X�n���g�����Ă�肽���̂ł�������Ă��悢�A�ȂǂƔ����Ȕ����������B �Ȃ�炩�̗��R�ŃX�n���g�����������l�X�����x�̓��@�����ŕ\�����Ĕ������n�߂��B�������A�������������ɉ䖝�Ȃ�Ȃ��̐l����������B�C���h�l�V�A�̎傾�����l��NGO�������őg�D���Ă���Kontra�i�s���s���҂Ɩ\�͋]���҂̂��߂̈ψ���j�́A6���̃A���^���ʐM�ɂ��ƁA�u�X�n���g�̕a�C�𗘗p���āA�X�n���g�̉ߋ��̔ƍ߂�Y�ꂳ���悤�ƎЉ�ɓ��������鐨�͂�����v�Ƃ̃R�����g���o�����B�X�n���g�̍v���͑哝�̂Ƃ��Ă̓��R�̋Ɩ��ł���B�X�n���g�̐����I�\�͂̋]���҂��Y�ꋎ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ԈႢ�͊ԈႢ�ł���A�X�n���g�̔Ƃ����ƍ߂͂����܂ł��Njy����˂Ȃ�Ȃ��A�Ƌ��������B �|�X�g�E�X�n���g����10�N�ڂ̂��܂Ȃ��C���h�l�V�A�Љ��������T�������A�X�n���g�̕a�C���@�ɂ�����Ƃ̂����������ł���B  ���āA�X�n���g�͂��ꂩ��k�������ċA��̂��A����Ƃ����������ċA�邱�ƂɂȂ�̂��B �`�F���_�i�ɂ���X�n���g�̂����~�͕a�@����k�̕������B�a�@���瓌�̕����������A���������W�����̃\���̒�������B�\���̓X�n���g�̍ȃe�B���̌̋��ŁA���̍x�O�ɑs��ȃX�n���g�Ƃ̕揊�A�X�^�i�E�M���E�o�O���i�ʏ̃X�n���g�_�j������B �����ł̓X�n���g�v�l�̃e�B�������łɉi������ɂ��Ă���A�v�ł���X�n���g�̂��A���҂��Ă���B�X�n���g�_�̓\���̉��ƃ}���N�k�S���Ƃ̕揊�A�X�^�i�E�}���K�f�O�̋߂��ɂ���B�e�B���̓}���N�k�S���Ƃ̖����̏o�ł���B�W���N�W���J���^�ߍx�ň�����_�Ƃ̏o�̃X�n���g�Ɨ͂����킹�ăX�n���g������z���������B���̉h�͂��ɂ͖{�Ƃ̃}���N�k�S���Ƃ��͂邩�ɂ��̂����̂ƂȂ����B �X�n���g�_��1970�N��A�X�n���g�����͂������Ă܂�10�N�ɂȂ邩�Ȃ�Ȃ����̂���v�悳��A���N�������Ċ��������B�s���~�b�h���������t�@���I���v���o������X�n���g�炵���p�ӎ������ł���B�v��̒i�K�ł͍H��͓����̕ăh�����Z��1,000���Ƃ����Ă����B����ȑ�����������ǂ���������o�����̂��A�Ɗw�������X�n���g�R�c�s�����N���������ɂȂ����B�X�n���g�͂���������Ԃ����B �����ł܂��A��76��Ɉ��p�����z�b�u�X�̌��t���v���o�����B����ȕx�A�傫�Ȗ��_���l�����邱�Ƃ͗͂̂��邵�ł���A���̏ꍇ�A�s�ׂ̐��A�s���Ȃǖ��_�Ƃ͂Ȃ�̂��������Ȃ��\�\���_�Ƃ͂����͂ɑ���]���݂̂ɂ������Ă��邩�炾�B �C���h�l�V�A�̐V���ɂ��ƁA���N����X�n���g�Ɋւ���{�����X�ɕ��сA���̔���s���������Ԃ�悢�Ƃ����B�w�X�n���g�`�\�N���X�N�i�X�n���g�̐��n�j����N�[�f�^�[�܂Łx�w�X�n���g�̃����T���ƕx�x�w�C�X�����̃C���[�W�����߂��X�n���g�x���76��łӂꂽRetnowati Abdulgani-Knapp��Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President�Ȃǂł���B�X�n���g�̓��@�����ō����͂����Ɣ���邩������Ȃ��B �V�X�@���������q �X�n���g��1��4���̃v���^�~�i�����a�@���@�ȗ��A�d�ĂƂ��̈�i��ނ��J��Ԃ��Ă���B�W���J���^�́w�R���p�X�x�d�q�łł݂�ƁA��Ã`�[���̌����Ă�1��13���ߌ㌻�݁A������s�S�ɂ��������Ă���X�n���g�̉̉\���͌ܕ��ܕ����������B�S�x�@�\�͒ቺ���ċz��̏���������Ă���B�����œ����Ă���͔̂]�Ə����튯�����Ƃ����B �C���h�l�V�A�̐V����ʐM�Ђ́A�\���x�O�̃X�n���g�_�̗l�q��͂��߂��B�����������n�߂�悤�A���͂Ȃ������ǂ����ȂǁA���ɐq�˂Ă���B�d�ԂƂ͂������̖{�l���܂��a���ɂ��邤���ɁA�挊���@���ď������Ă����A�Ǝw������悤�ȉƑ��͂��Ȃ�����A�L�҂Ƃ͉���ʂ��Ƃ����̂ł���B 13���ߌ�ɂ̓X�n���g�̐e�����F�l�̃��[�E�N�A�����[���V���K�|�[�����W���J���^�ɗ��ăX�n���g�����������B�Ō�̂��ʂ�̂��肾�����̂��낤�B�X�n���g�ӎ����Ȃ��A�X�n���g�̉Ƒ������Ă��������������A���F���ăV���K�|�[���Ɉ����グ���B ���h���m�哝�̂��J�����哝�̂��X�n���g�̕a�C�������ɏo�����Ă���BAP�Ȃǂ̊O���ʐM�Ђ̓X�n���g�̕a��̋L���Ɂu���\�ŕ��s�����ƍَҁv�Ƃ����`�e�����邱�Ƃ�Y��Ȃ����A�C���h�l�V�A�̑����̎x�z�w�̓X�n���g�������������Ă���B12���̓X�J���m�̑��q�̃O���[�E�X�J���m�v�g�����a�@�������ɍs�����B13���ɂ̓C�X�������̐l�C�����t�A�A�E�M�����X�n���g�����������B�X�n���g�����������l�X�̃��X�g���ꗗ�\�ɂȂ��ďo�ȕ\�̂悤�ɔ��\�����Ɩʔ����̂����B  1998�N�̎��r�E���ވȗ��A�X�n���g�͍��v10����̓��މ@���J��Ԃ��Ă����B���@���J��Ԃ����тɂ��낻��X�n���g�������Ă�낤�ł͂Ȃ����A�Ƃ����������܂����B����͂��ꂪ�ō����ɒB���Ă���B ����ŁA9.30������̑�ʎE�C�A���e�B���[���̎E�C�A�A�`�F�̎E�C�A�^���W�����E�v���I�N�����ł̃C�X�������k�E�C�A����ɂ��킦�ċ��K�I�ȕ��s�A�X�n���g�ᔻ�����ւ̗}���A�ȂǂȂǂ������Ă��܂���̂��Ƃ����������܂��Ă���B �哝�̂̃X�V���E�o���o���E���h���m��12���A�}���[�V�A�K���\���萔���ԌJ��グ�ċA�����A�X�n���g�����@���̓X�n���g���߂��鏔���ɂ��ċc�_��T�����ł͂Ȃ����Ɣ��������B�X�n���g�ɉ��₩�Ɏ���ł��炢�A�X�n���g�̎��ƂƂ��ɃX�n���g�Ɋւ��Â��L�����Y�ꋎ���A�X�n���g��̃C���h�l�V�A�����������Ă��镉�̈�Y���A�X�n���g�Ƃ��ɖ�������邱�Ƃ�����Ă���̂�������Ȃ��B���������ăX�n���g�i��h�ƃX�n���g�ᔻ�h�ɕ���A�哝�̂Ƃ��Ă��̑Η��Ɋ������܂��͔̂��������Ƃ����Ƃ��낾�낤�B �w�W���J���^�E�|�X�g�x��8���̎А��Łu�퍐���Ȃ̂܂܂ŃX�n���g�ٔ����s���āA���̌�ő哝�̂����͂�����悢�v�Ƃ����߂������Ă����B�C���h�l�V�A�l�͋����̂����ӂŁA�Y����ۂ��̂����������A�������ɃX�n���g�Ɋւ�鎖���͖Y�ꋎ��ɂ͏d�߂���Ɠ����А��͂����B�����A���̂悤�ȓW�J�ɂ͂Ȃ炸�A�킯�̕�����Ȃ��`�ł���ނ�ɂ���̂��ŗǂ̐��������Ƃ�����@���Ƃ��邱�ƂɂȂ�̂��낤�B �W�O�@�n�W�E���n�}�h�E�X�n���g�@�@1921-2008 �C���h�l�V�A�̑�2��哝�̂߂��X�n���g�i�C�X�����̌ď̂ł̓n�W�E���n�}�h�E�X�n���g�j��2008�N1��27���A���@��̃W���J���^�E�v���^�~�i�����a�@�Ŏ��������B86�������B�X�n���g��1��4���A�̒�������ăW���J���^�E�N�o�������̃v���^�~�i�����a�@�ɓ��@�����B�₪�ďǏ�͑�����s�S�Ɏ���A�d�Ăȏ��������B�X�n���g�̈�t�c�́A�X�n���g�̋��ٓI�Ȑ����͂Ɋ��Q���A����A�X�n���g�̉Ƒ��́A�l�H�ċz����͂������ǂ����̔��f����t�c�Ɉ�C�����A�ƕ��ꂽ�B1��15���ɂ̓X�n���g�Ƃ̎������ɂ�����l�����A�n��̍s���ӔC�҂�R�E�x�@�̎傾�����l�X�ƂƂ��ɁA�����W�����E�\���x�O�̃X�n���g�_�i�A�X�^�i�E�M���E�o�O���j�����@�ɖK�ꂽ�B���}�����鏀���͂��ł������Ă���ƃX�n���g�_�̊W�҂�������A���邢�́A�v���^�~�i�����a�@5�K�ɂ���X�n���g�̕a���ł͔ނ̃x�b�h�̈ʒu�����b�J�̕����������悤�ɕς���ꂽ�A�ȂǂƐV�����`���Ă����B �X�n���g�̕]���ɂ��Ă͔ے�ƍm�肪�܂���ɕ�����Ă���B1998�N�ɔނ��哝�̂̍���ǂ�ꂽ�Ƃ��͗l�q��������B���̂���́u�X�n���g��݂邹�v�Ƃ̋��ѐ����X�n���g�i��̐������������Ă����B���ꂩ��10�N�B�X�n���g�����@����1��4-14���ɊJ���헪�����Z���^�[�iPuskaptis�j���s�������_�����ł́A�҂�67�p�[�Z���g�u�X�n���g�������v�Ɖ����B �X�n���g�̌�p�哝�̃n�r�r�̓X�n���g�F�̑ŏ����ɖ�N�ƂȂ����B����̓X�n���g����̕��s��|�����߁A�X�n���g�͕s���~���e�^�ŌY���i�ǂ��ꂽ���A�n�r�r�������A���q�h�������A���K���e�B�������A���h���m�������X�n���g�Ƃ��̎�����ق����Ƃ��ł��Ȃ������B���ǁA�X�n���g��10����̓��މ@���J��Ԃ����ʂĂɁA�X�n���g�������Ă�낤�ł͂Ȃ����Ƃ����������A�@�I�Ȃ����߂�����ׂ����Ƃ��������傫�����f�B�A�œ`������悤�ɂȂ����B�X�n���g�������Ă�낤�ł͂Ȃ����A�Ƃ������̔��M���́A�X�n���g����ɃX�n���g�����̔�Ő��ɏo�āA�X�n���g��̂��܂��Ȃ��炦�Ă��钆���̌��͎҂⎑�Y�Ƃ����ł���B�X�n���g���������A�ނ�̐����̔閧���܂����ɂ���Ȃ��ł��ނ���ł���B �Y�������Ƃ��ẴX�n���g�̕s���~���Ɋւ���ٔ��̓X�n���g�̌��N��̗��R�Œ��f���ꂽ�B������ĕs���~���Ԋ҂̖����i�ׂ��N�����ꂽ���A���̍ٔ������X�n���g�̍��Ƃւ̍v���Ɍh�ӂ�\���Ď�艺����ׂ����Ƃ̐����X�n���g�ɂȂ���l�X���獂�܂����B���h���m�哝�͖̂����i�ׂ����k�ʼn�������悤������������X�n���g���ɒ�Ă��������A�X�n���g���ɋ��ۂ��ꂽ�B���h���m�͂��̂悤�Ȏw���͂��Ă��Ȃ��Ɣے肵���B  �ȏ�̂悤�ȁu�����v�u�����ʁv�̋c�_���������钆�ŁA�x�b�h�̏�̃X�n���g�͈ӎ��������A�����ǂ��A�܂������Ƃ���Ԃ��J��Ԃ����B���Ă̍��Ǝw���҂������������ĐÂɌ����낤�Ƃ������͋C�ł͂Ȃ������B�X�n���g��1��13���Ɍ����������[�E�N�A�����[�̒k�b�����̂��Ƃ��Ȍ��Ɍ�����B�X�n���g�̒��炭�̗F�l�ł��郊�[�E�N�A�����[�̓X�n���g�����������̂��A�V���K�|�[���Ŏ��̂悤�Ɍ�����B�u�������ɕ��s�͂������B�Ƒ���F�l�ɕX���͂������B�����A�o�ϐ����Ɛi���������炵���̂��v�B���[�E�N�A�����[�͌o�ϐ����̌��тƕ��s�E�}���Ƃ������̈�Y�������������A�Ȃ��X�n���g�̌��т͑傫�������A�ƕ]�������B�u�C���h�l�V�A�����̓X�n���g�����čK�^�ł���v�ƃ��[�E�N�A�����[�͌������B���̃X�n���g�����̕a���ɂ���Ƃ��A���тɑ����������h���Ă��Ȃ����Ƃɔ߂��݂�\�������B ����̓X�n���g�i��̔����ł���ƂƂ��ɁA�����I�}�����R�X�g�Ɍo�ϓI�����𐬂������A�L���ł͂��邪�S�n�����s�s���Ƃ����肠�������[�E�N�A�����[�̎��ȕٌ�ł��������B���[�E�N�A�����[���X�n���g��1960�N�㔼����A�����I������`�A��{�I�l���Ȃǂ̐����I���l�ƈ��������ɁA���͂Ȓ����W���̐��i�A�W�A�I�����`�Ə̂����j�����肠���Čo�ϐ����E���Ƃ̃C���t���X�g���N�`���[�Â���ɗ�B 1960�N��ɂ͕n�����ǂ�����Đ����Ă��������̂��Ƃ�����Ԃ����������ɖL������^���Ă�����B�����`������ŐH���Ȃ��ł�����́A�ق炳��Ă͂��邪�\���H�����炵�̂ق����ǂ��ł͂Ȃ����B���ꂪ�A���[�E�N�A�����[�̎��_�ł���A�X�n���g�]���̊�ł���B �u�j���[�I�[�_�[�v�Ƃ�ꂽ�X�n���g�̐����̐���32�]�N�̎��̗���ɑς��A�C���h�l�V�A��1�l�������������������1965-1996�N�̊Ԃ�4.5�{�������āA����𑱂���l���ɂ�������炸�����ɖL���������������B�������A����ŁA�C���h�l�V�A�l�ɐ����I�v�l��~�����v��������ł��������B �X�n���g�͒����W�����̔_�Ƃ̎q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�I�����_�A���n����A���{��̉��A�C���h�l�V�A�Ɨ��푈�A�Ɨ���̌R�o���������j���������B������̒鉤�Ƃ��ăC���h�l�V�A�ɌN�Ղ��Ă����X�J���m��Ǖ����ăC���h�l�V�A���Ƃ��蒆�Ɏ��߁A�G��ƂȂ����B�����I�������܂�Ă���Έ̑�ȉp�Y�ƂȂ肦���B�W�������g�L�b�G�g�h�A���邢�̓C���h�l�V�A���g�i�|���I���h�Ə̂���ꂽ��������Ȃ��B���A������A�X�n���g�������Ă���20���I�́A�����`�A�����A�����̌��i�ȋ�ʁA�����Ȃǂ����l�Ƃ���鎞�ゾ�����B �X�n���g�Ƃ��̎��ӂ̌R�l�́A�ނ�̐��̎w���҃��n�}�h�E�n�b�^��X�^���E�V���t�����̂悤�ȊO���ł̍���������Ă��炸�A�����`�Ȃǒm��Ȃ������B �X�n���g��1965�N��9.30������ɁA�C���h�l�V�A���Y�}�ɑ��ĕ����I�r�ō����s���A��10���l����100���l�Ƃ����铯�E�̎E�C�ɊW�����B���e�B���[���N�U�A�A�`�F�̕����h�Ƃ̃Q������͂��Ƃ��A���������ɂ������Ă��^���W�����E�v���I�N�����ȂǁA�\�͂̎g�p�����߂��Ȃ������B�X�n���g����̃C���h�l�V�A����j�͗��������ň��Ă���B 9.30�����̐^���Ƃ��̌�̓��E��ʋs�E�����̏ڍׂ͂��܂��ɕs���ł���B�^���̓X�n���g�������ŕ���Ă����B�X�n���g���r����10�N�ɂȂ邪�A���܂Ȃ��^�������ւ̐ϋɓI�ȓ����͌����Ȃ��B�Â����j�̊W���J����̂��F���|�����Ă���̂��B ����͎��̂悤�Ȏ���ɂ��B�C���h�l�V�A���Y�}���₻�̎��ӂ̐l�X�͕��m����ďe�Ō����ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B�C���h�l�V�A���R�ɂ����̂�����A�R�����n���ꂽ�����A�萻�̎R���A�蕀�A���_�ȂǂŁA���Ԑl�̎�ɂ���ĎE���ꂽ�B�C�X�����@���c�́E�i�t�_�g�D����E���}�̎w���҂ŁA�̂��ɑ�4��哝�̂ɏA�C�����A�u�h�D�����t�}���E���q�h�͂��āA�C�X�������k��50���l�̃C���h�l�V�A���Y�}�W�҂��E�Q�����ƌ�������Ƃ�����B �C�X�������k�ɂ�鋤�Y��`�҂̎E�C�Ƃ������c�Ȏ��������邱�ƂȂ���A���̑�ʎE�l�����Ɋւ��āA���͎҂̗⍓���A���邢�͗⌌�Ƃ������̂ɔw�������Ȃ�v��������̂́A���̃C���h�l�V�A�l�ɂƂ��ď����邱�Ƃ̂Ȃ��g���E�}�ƂȂ��Ă��関�\�L�̎S���A���邢�͗��j�I�ߌ����A�w��ʼn��o���Ă����l���������Ƃ����_�ł���B �X�n���g��9.30������̋��Y�}���ɂ��āA���Y�}�r�ł̂��߂ɌR�ڎg�������A�ނ���A�����ɕ����^���ނ�̎�ŋ��Y�}�ɑŌ���^����I���������ƁA����������O�̂悤�Ɍ�������Ƃ�����B 9.30�����ŎE���ꂽ���R�����̈�̂����āA�X�n���g�́u���Y�}��j�邱�Ƃ����̍ő�̋`���ł���v�Ɗ����A��s�ł���A�n���ł���A�R���̉B��Ƃł���A���Y�}�̒�R�ӂ��錈�ӂ��ł߂��B�������A���̓����ɂ͌R�ڎg�������A�u���͍����������h�q���A�ނ�̎��肩����̍�������|����̂Ɏ��݂��ق���I�v�Ǝ��`�w�X�n���g�\�\�킪�v�z�ƌ��s�x�Ō�����B�����̊Ԃ̔��ځA���Ƃ��C�X�������k�Ƌ��Y��`�ҁA�x�T�w�ƕn�_�̊Ԃ̑Η��𗘗p���āA�����ɕ����^���č���܂ł̗אl���E�����邱�Ƃɂ���āA���͎҂ւ̓���˂��i�̂ł������B�����I�Η��͗����Ɏ���Ƃ������|�̎���������Ɍ������A�����𐭎��I�Ɉނ������邱�ƂŒ����Ԃ̌��͕ێ��ɐ��������B �����A�ق�Ƃ��ɂ��������R�X�g�Ȃ��ł́A�����̃C���h�l�V�A�͂��肦�Ȃ������̂��H �����X�n���g�Ƃ͈Ⴄ�^�C�v�̎w���҂�����30�N�ȏ�ɂ킽���ăC���h�l�V�A���^�c���Ă�����A���܂��������Ƃ܂��ȃC���h�l�V�A���o���オ���Ă����̂ł͂Ȃ����H�@�c�O�Ȃ���A���������₢���āA�C���h�l�V�A�͂���10�N�ԁA�[���ł���悤�ȓ������������������Ƃ��ł��Ȃ��܂܂ł����B�����������邤���ɁA�X�n���g�̓C���h�l�V�A�l�̎肩��X�����Ɣ����Ă��̐��ɗ������Ă��܂����B |